「家庭の幸福は諸悪のもと」と太宰は言うた。それで泣いてるのは街だと困る。

太宰治の『家庭の幸福』という短編がありましたねえ。
戦後すぐ話なのですが、役所勤めの30歳が主人公で、ラジオというその頃の先端を象徴する家電(耐久消費財)を通して、いかに「家族」が物質的欲望を具現化する共同体となって、その無意識=エゴイズムが他者をいかに損なっていくか、というとんでもない今的な予言めいた作品で、「曰(いわ)く、家庭の幸福は諸悪の本(もと)」という最後のやつです。
この「家庭の幸福」は、
主流のOSは、「ジジババ」の財産は「ジジババ」個人のものだ、とテレビの中から語りかけてきます。
と同じ類のもので、個人の欲望がすなわち「極めて家庭的な家族」の欲望であるという、〈近景〉のなかの〈共ー欲望〉なのだと思うわけです。
家族というのは、一体何なのでしょうか。
オレは岸和田の商店街で4人兄弟の末っ子で育ちましたが、ガキの頃お向かいの瀬戸物屋さんにしょっちゅうカレーライスやうどんを食べさせてもらいました。
昭和40年代初期のころは、岸和田でなくても街的なところではそうだったと思います。その瀬戸物屋さんには同世代の3人の子どもがいたのですが、オレは休日の昼になると彼らと一緒にメシを食ってました。メシを「よばれて」それから家に帰るのです。自分の家では同じ時間にオレ以外の兄姉と家族揃って休日の昼飯を食っているのに。今から考えるとおもろいですね。
その瀬戸物屋さんは江戸時代から続く大店で、それこそ完全な大家族で、おじいおばあ(この「むかいのおばあちゃん」の洋服姿は亡くなるまで一回も見たことがない)の夫婦と、その息子と若奥さんの夫婦と3人の子ども、住み込みの丁稚さんから番頭さん、女中さん、それから休日のオレがいたわけです。この話を上の姉にすると「わたしも小学生の時はそうだった」といってます。
家族は〈近景〉ではなく〈中景〉のほうがわかりやすいですね。やくざの一家が疑似家族に例えられるのは、まさにそうで、もともと同じ度量衡を持たない違ったメンバーが、同じ空間や時間を短期的にしろ「共有」する。「共有」というのは「所有の権利」を示す語意ではなく、そこには「頭(カシラ)」がいて「右腕」がいて「手足」がいる。「目利き」も「腹心」、「腰巾着」もいるかもしれない。
「主―従」「国王―諸侯」といった制度的あるいは契約的関係性の集合体じゃなくて、完全に一つの人のメタファーですな。そこでは〈共―身体的〉なというか、とても〈共―身体的な共―欲望〉が、ゆるやかに作用しているということです。
家族としての構成員全員の欲望が一致するには、手も足も頭も肝もあって、ばらばらの部位が多すぎて難しいのだけれど、よく見ると確かに一つの固有の生理を持った「巨大な生物」のように動いている。
〈専制所有〉と違う〈共有〉はアリかと。
あたしは、「ジジババ」というのは、共有地(コモンズ)なんだと思うのです。それも「街場」のはね。街場の「ジジババ」はあたしらの共有財です。
とは、巧いこと言うてますね。
けれどもいま、大阪では金をそこそこ持ったネオ・ジジババが、また「街なかに住む」というリバウンド現象みたいなことが起こってい て、それで船場や江戸堀や京町堀の街中のマンションがよく売れてるということです。
広い庭と4ドアセダンのクルマと犬だけが残っていて、子どもだけがいなくなった箕面や池田や千里ニュータウンの「家」から街中のマンションへという志向性は、空間が誰か(この場合、自分)の所有だけで構成されているという、ある種の「居心地の悪さ」、いいかえると「よりどころのなさ」からの脱却を指し示しているのだと思います。
鷲田清一せんせと大庭健さん編の「所有のエチカ」で、大庭さんは今的風潮として「所有領域の中ではミニ専制、無所有領域では放縦」という傾向があるといってます。これは個室のような「専制所有」の空間の中では「ここは私の部屋やから何をしてもいい」という意識が強まり、逆にほかの誰かの所有とわかるところでは、その領域やその空間の中の物
に極力触れないようにするが、誰も私有しない「公」には全く無関心で、そこでは何をしてもいいと考える。
そういう現代社会は「没公共的な私有社会」であると大庭さんは言ってます。公園と同じようにだから家庭内でもリビングやキッチンのような公共空間が縮小するか荒れるのでしょう。こないだも書いてまたしつこいですが、こっちにとっては公共の空間であるはずの洗面台は女房(別れましたけれど)のもので、だからちょっとでも歯ブラシの置き位置を変えただけで、オレは烈火のごとくしかられました。
そういうふうに、経済的豊かさと物質的欲望を実現する単位として、つまり消費共同体としての〈家族〉が、どんどん「所有する〈個〉」の集合体に微分化されている。携帯電話はじめ共用ではない「ひとりユース」に照準した商品が生活を豊かに、かつ自分らしくする。それと同様の発想で「家族」の構成員の「所有物」の総和としての住居つまりハコとしての「家」が存在し、ジジババもその構成員とするのなら、ちょっと違うのではないかと思ってます。
以前、雑誌ミーツの「街的生活本」という特集で、30代のルームシェアの人々を取材しましたが、彼らの〈家〉つまりハコでは公共の場所はトイレと風呂場だけしかなく、それがものすごく汚かったのを思い出して、そういえば共同のリビングってあったかなあ、と出てこないのです。
言うときますが、そのルームシェアの成員は「ニート」とか「フリーター」とかでなく、きちっとした仕事をしてる所謂「イケてる」30代前半の男女。広告代理店とかITとか方面の若者で、フォークシンガーの「イルカ」な感じが皆無なのに「パートナー」とか「同居人」とか言ってるところが、その便所の汚さと相まってとても気色悪かった。
そういう家=ハコで育った子ども(大人も)にとって、駅や車内やスターバックスの席は公共空間であることや、そもそも公共空間がどんな状態でこの世にあることが知らないかもしれません。そうなると自分の身体だって疑いのない私有物だから電車で化粧もするし、ものも食べるのでしょう。唇にピアスをはめたり、腕や足首に彫り物を入れたり平気でするのもそうでしょうか。
そういうやつは新世界の串カツ屋で「2度づけお断り」の意味が分からない。多分、横のおっさんにどつかれても分からないかもしれません。「西成って怖いところですね」みたいなかんじで。
一方で、「いま―ここ」でナマの身体付きのリアルなコミュニケーションがやり取りされる場というのは、今流行りの「カフェ的店」が典型で、その北欧的なセンスを自分の部屋に取り込もう、なんて雑誌の特集 がされている。
なんでこんなことになってしもたのでしょう。内田樹先生は
制度的には互いに有責なのだが、その制度的有責性が大枠を保証しているせいで、濃密な人間関係を取り結ぶ必要がなく、成員たちが適当にふらふらしていても大丈夫な家族。家族の一人が何年も家をあけていて、ひょっこり帰ってきて「ただいま」と言っても、「お帰り」と何事もなかったかのように迎えてくれる家族。
と相変わらずええこと書いていますが、ウチの岸和田の家では、家がほとんど店舗でリビングなんてなく狭いからこそ取引先の「業者」とは近くの喫茶店で話していたし、母親が商売が忙しくてじゃまくさいから兄貴とオレは、ガキの頃から外でお好み焼きやたまには焼肉を食っていた。
要するにみんな街場では「実生活者」で「消費者」なんていうものではなかった。そういうふうに思うわけです。

2007年12月20日 08:37
このエントリーのトラックバックURL
http://www.140b.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/189
Listed below are links to weblogs that reference
「家庭の幸福は諸悪のもと」と太宰は言うた。それで泣いてるのは街だと困る。 from 140B劇場-浅草・岸和田往復書簡
トラックバック
太宰治『家庭の幸福』 ... ...
(集英社新書 426B) (集英社新書 426B) 隈 研吾/清野由美(著) 2008年1月22日 集英社 720円+税 ...
『日本文明・世界最強の秘密』 増田悦佐(著) 2008年3月7日 PHP研究所 1600円+税 ...
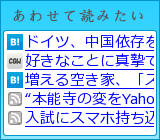
コメント
コメントを送ってください