テレビ村という共同体。
マルクスの自然哲学もししくは普遍経済学
マルクスは、「人間が精神的ない
し身体的に自然に働きかけると、 自然は価値化する」といっていま す。人間が働きかけると、ただの 自然ではなくなって「価値的自然 」になる。人間の延長線になって 、人間の役に立つような価値を生 じる。したがってそれは人間の身 体の延長線になると、マルクスは そこまではいっています。/では そのとき人間はどうなるかという と、人間は逆に自然になっちゃう んだといっています。/(中略) ……どこをどう考えても、これだ けはまだ生きつづけるよと思って います。(吉本隆明:『日本語のゆくえ』:p71-73)
江さん、お久しぶりでございます。ひとつきも間があくと、江弘毅用脳みそに錆びが浮いていて磨きをかけるのに時間がかかります。それで自分のブログでリハビリをしておりましたけれど、その間、大阪には新しい府知事が生まれていたのですね。その結果については、あなたも疑問を呈されていますが、あたしも、なんだかなぁ、なのです。
大阪府知事選について
内田樹先生もそのことには触れていますが、(たぶん)意図的に皮肉をこめて楽観を装っていらしゃるように思いました。
私にはこの事態は「アメリカ化」というよりは「演芸場化」という方がことの本質を言い当てているような気がするのである。/そして、繰り返し言うように、私はそれを別に悪いことだと思っていない。/もし演芸場で国政を議しても、とくに大きな支障がないというような統治システムを私たちが完成させたのだとすれば、それは政治史上に残る達成として久しく言祝がれるべきであろう。/いや、ほんとに。[演芸場国家ニッポン (内田樹の研究室)]
内田先生は、「別に悪いことだと思っていない」と書いておられますが、あたし的は「もうどうしようもない」といったほうがよいかと思うのです。そして内田先生にはその「しょうもない」を「しょうもないではすまされない」と切り込んでほしかったのでした。
「しょうもない」を「別に悪いことだと思っていない」とやりすごしてしまうと、こんどは「どうでもいいや」がやってきて、それは「考えること」の終わりのような気がしてしまいます。なので、なにか強迫観念のように、あたしは「別に悪いことだと思っていない」とは思いたくないのですが、もちろん「別に悪いことだと思っていない」からの思考は可能ですけれどもね。
そしてこれは演芸に対する感覚的な問題ですが、あたしの知る限り、演芸場はテレビとはあきらかに違う〈磁場〉を持って存在しているのだと思います。芸事はテレビの世界では表現しきれるもんじゃないく、テレビに映し出される芸事は、どこまでいっても真性の偽者でしかありません。なので、内田先生がいう「演芸国家」は正確には「テレビ国家」と呼んだ方がよいかと思うのです。
テレビ村という共同体
いまや、テレビが共同体性の欠如(「街的」の欠如)を、機能代替的に穴埋めしているんだろうな、と思うのです。TVは一番身近なご近所で、隣の住人の名前もしらないくせに、テレビにでてくる人のことは知っていたりします。それもただ知っているのではなく、芸名ばかりか、本名や、生年月日、学歴、出身地、そしていまつきあっている相手までも、一方的に知っています。
いまや、テレビに出てくる人こそが〈私〉の(一方的な)一番の知人なのであって、〈私〉はテレビに向かって笑い、泣き、憤慨し、喜び、そうしてテレビを中心にして〈私〉の「世間」(円環)はできあがっています。 それをあたしは「テレビ村」(TV村)と呼んでいますが、橋下さんが大阪府知事選に立候補したとき、
TVの世界に棲む芸人というのは、じつはかつての芸人(つまり非社会的な民であり、悪党である)とは違って、今や、世間にとっては最も身近な円環の中の住人であるということだ。/これは「宮崎県知事選挙でそのまんま東氏が当選したこと。」でも書いたが、つまりテレビは今や、われわれにとっての(仮想的な、心的な)ムラ社会なのである。つまり共同体の機能等価物である。そこで見られる者に匿名性はなく、ゴシップに溢れていることで、われわれのムラ的な心理を満足させようとしている――ことでテレビは益々芸能的になる。そしてそこで生き残るためには芸人はムラ社会的に規範的である必要がある。 [テレビという共同体と芸人の進化的戦略―加護ちゃん引退。]
という(自分で書いたテクストを引用し)橋下さんは、べつにどこの公認を受けなくても当選確実だろうと書きました。
その理由は簡単で、浅草に住むあたしは、橋下さん以外の候補者を知らないからに他ならず、たぶん大阪のおっちゃんも、おかんも、同じテレビ村の住人として、橋下さん以外を知らないのだろうな、と思ったからです。つまりその根拠は、橋下さん以外はテレビに出ていないから、というべらぼうなものです。
環境管理型権力というしばり
しかしこんなべらぼうがまかり通ってしまうことに、この国の困難があるように思います。江は「うんと固くしばってくれると、か
それはけっこう固いしばりだったりするのですが、しばられている本人がしばられていることに気付かない、というしばりです。
あたしたちはTV村という「世間」にしばられれている。これがやっかいなのは、しばりを意識させない(感じさせない=考えさせない)からであって、だからあたしたちはますます「考えること」をしない。そのことでつまりは「どうでもいいや」になってしまうんだと思うのです。
それを社会学では環境管理型権力とか呼ぶのでしょう。マクドナルドの椅子は(客の回転をよくするために)固く出来ていて、10分以上座っていられないようになっている、という工学的なしばり、つまりはマクドナルド化です。
贈与的な時間軸の欠如
先日、吉本隆明さんの『日本語のゆくえ』を読んだのですが、吉本さんは、いまの若い人たちの詩を評してこういうのですよ。
いってみれば、「過去」もない。「未来」もない。では「現在」があるかというと、その現在もなんといっていいか見当もつかない「無」なのです。(『日本語のゆくえ』:p206)
そしてそれは「自然」への働きかけ、自然そのものがなくなってしまったからだろう、と。それは、あたしの語彙で記述すれば、贈与主体としての〈私〉の貧困、なんだと思うのです。いってみれば「考えない〈私〉」なのですが、考えなくとも日常的には支障もなく、むしろ楽な日常だったりするので「別に悪いことだと思っていない」のでしょう。
冒頭に示した「マルクスの自然哲学もししくはバタイユの普遍経済学」の、あたしの勝手な理解をむりやり引っ張り出せば、テレビ村には、純粋贈与という自然、そしてその自然に働きかける贈与主体としての〈私〉がありません。つまり《「過去」もない。「未来」もない。では「現在」があるかというと、その現在もなんといっていいか見当もつかない》というのは「贈与」のもつ時間軸の欠如なんだろうと。
そしてそのために、「自然」への働きかけ、自然そのものがなくなってしまったからだろう、なのだと思うのですが、それはつまり、「自然」がなくなってしまったのではなく、「自然」に働きかける〈私〉がなくなってしまったのだと思うのです。もちろん純粋贈与という「自然」には、人間という自然も含まれますから、〈他者〉は消えてしまいます。
あたしたちはいま、時間の経過とともに〈私〉は変化する、そしてその変化を受け入れて生きる、という贈与の感覚を失ってしまっているように思えます。つまりそこにはキアスムがない。その根本原因はやはり「象徴の貧困」なんでしょう。いまやあたしたちの象徴界に、国家のようなマクロ共同体はありません。
もちろんあたしは国家(というか特定の権力=うんと固くしばっくれるもの)なんぞが(象徴界に)居座る必要はなく、ただ日本人が考えるための言語としての日本語があればいいのよ、といってきたのですが、しかしいま、そこに居座るのは「交換の原理」です。
それはお金を入れれば、ガチャンと商品がでてくる自販機のような、等価交換に支配された〈世界〉です。共同体は本来「贈与」のかたまりのような場であるはずなのに、TV村には「贈与」がありません。それがなぜかといえば、TV村の基本原理が「交換の原理」だからでしょう。若さ(時間軸の否定)さえ金で買えるような時代です。TV村ではプチ整形とかアンチエイジングが大流行です。そこでは「自然」が消えてしまっています。
私有
勝手な理屈ね。人間て、そんなものじゃないわ。男でも女でも、たれかの持ち物でなくちゃ、生きてゆけないものよ。子供は親の持ち物だし、親は子供の持ち物だわ。男とか女がいい仲になれば、お互いはお互いの持ち物だし、持ち物でない人間ていないわ。あれば、きっとそれは人間の形をしているだけで、野良犬よ。(司馬遼太郎:『風邪の武士 上』)
《子供は親の持ち物だし、親は子供の持ち物だわ》は、あたしの神経逆撫でフレーズのベストなのでここで紹介するわけですが、この感覚にはずっと気持ちの悪いものを感じていました。
男女の間での所有の感覚はわかるとしても、子供が親の所有物として、例えば母親の子宮にぶら下がったままであるかのように、母親が、子供の試験会場に付き添い、入学式に付き添い、はては入社式にまで付き添い、いきおい新婚旅行まで付き添うような、そんな母親の私有物として育った子供はどうなるんでしょうかね、というか、この国にそんな時代があったためしもない。
それは「分離-不安」という動物的な親-子関係が永遠と続いているかのようで、どこか動物的なものを感じてしまうわけですよ。つまりねペットとしての犬が幾つになっても子供の機能代替物であるようにです。
しかし、そのかつてなさでさえ、子供は親のもんだ、親は子供のもんだ、といわれりゃ返す言葉もないし、富国強兵でもないですからね、子供は国の宝だ、などと今更いっても仕方がない。
ただ、公共のものとしての子供、たとえば街が子供を育てる、といった感覚の欠如は、じいさんとばあさんが街の公共物であることを忘れてしまったこととダブるわけで、それは(たぶん)「贈与」としての共同体性の問題なのですが、その共同体性がTV村のように「交換の原理」で動くものに駆逐されたとき、「街的」という共同体性もその不思議な私有感覚のなかに埋没してしまっているように思います。
そこであたしは、「ああ、いやだ、いやだ」と駄々をこねるしかないのですが、だからこそ、あたしは、いまある「街的」を自らの意識のネットワークの隅々まで駆使して捕らえ、それをあたしの考える言語である日本語で書き続けたい。つまり、まだまだ、あきらめちゃいなのよ、ってことですね。
んー、脳みそ錆びてますね。(笑)
2008年02月03日 21:19

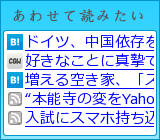
コメント
こんにちわ、内田さんのブログからとんできました。
すでにして国会が演芸場化、リング場化、養鶏場化している今日、演芸場で国政がうんぬんされることは別に悪いことではないし、そもそもどーでもいいことだと思います。
国会議事堂ってのはあれはお墓だそうですね。
てっぺんが円形ドームじゃなく、そのかわり伊藤博文の墓に擬したものをのっけているそうです。(日本の〈地霊(ゲニウス・ロキ)〉 鈴木博之/著 )
すでにしてここまでやっているのに、なにをいまさら演芸場かと思いますがねえ。
投稿者 イカフライ : 2008年02月05日 09:26
>イカフライさん
コメントありがとうございます。
国会議事堂がお墓であることは、どこかで聞いたことがありますが、けっこう笑えますね。
投稿者 ももち : 2008年02月12日 14:05
コメントを送ってください