経済成長が日本の大人をダメにした。
あたしの消費者時代の記憶(たいしたモノではないけれど)
情報の消費という情報
笑っちゃいけないんでしょうが、「編集会議」という編集者・ライターの塾みたいなものがあるんだと知って、思わず笑ってしまいました。しかし考えてみれば、あたしも「ブログの書き方」なんてことをやっているわけで、うかつには笑えないわなと。
それにしても「編集会議」での演習課題
「情報誌でない○×誌をつくる」
に対する
「読者からのいい店良いものを募りそれを編集する読者参加型の雑誌」とか「情報誌の情報を毎月検索できる」とか
は、じつにWeb2.0の教科書的回答です。ある意味素晴らしい。しかしそれは全てウェブでできることであり、紙媒体よりもデジタルが得意とするもので、いってみれば「情報の消費という情報」です。
その良し/悪しは別として、ウェブは「情報の消費という情報」に関しては天下無双なわけで、それを紙媒体でやったところで勝負にはならないでしょう。しかしそういう回答が「編集会議」(というテクストの専門家?)からで出てくるところに、インターネットが普通にある時代=Web2.0的時代の空気を感じます。
Web2.0と編集者
それは、あたしらの職業的語彙(イディオム)だと、User as contributor 若しくはParticipation そして Data as the intel inside ということになるのですが(横文字ばっかしですいません)、インターネットが普通にある時代である今、さらにはポータルサイト(一時代前の編集する権威)の力が落ちて、検索エンジンナビゲーションが主流である今、情報誌のライバルはウェブ(それもブログ)なんでしょうね。しかしウェブ的な発想を紙媒体でやったところで今更ですわ。
ウェブにある情報のほとんどは(あたしのテクストも含めて)屑でありゴミです(「情報の消費という情報」ですから)。つまりは、今という時代は、情報のゴミ箱のなかから情報を探さなくてはならないという、編集の貧困の時代でもあるのですが、その反面、とんでもない「めっけもん」もあったりします。
その玉石混淆のアホらしさ、「めっけもん」に出会う偶有性こそが、ウェブのダイナミズムなんだと思いますけれど、その偶有性を担保するために、ウェブは編集者を必要としていないのですね。(たぶん)。
しかし編集機能の代替を狙うものは当然にあるわけで、それは全て機械的にできています。たとえば検索エンジンはそもそもが機械的な編集ですし(検索順位の決定)、パーソナル化という指し示しもあります(たとえば、アマゾンだと、あなたはこういうものが読みたいでしょう、というおせっかい的な表示がありますが、それがパーソナル化という機械的な指し示しです)。
そういう機械的な指し示しを真に受けて、あたしは「こういう人なのね」と思うなら、それは〈消費者〉であり、個性化を装った「みんな」化でしかないのですが、しかしウエブはまだまだ玉石混淆なカオスなわけで、しいていえば、自覚的に情報を検索している自分こそが編集者となりえる可能性を残しています。
その意味では、ウェブはまだまだアナーキーになりえますし、パンクです。権威の誘導は(自覚的である限り、つまりは「私」となろうとする限り)要りません。
テレビ村は、最初から受動的な「みんな」しか対象にしていませんから、「みんな」を再生産することで、まだ権威であろうとしています、しかし情報のゴミ箱状態はウェブと五十歩百歩でございます。(朝の時間によくやっている、テレビの中の「新聞読み」は、「情報の消費という情報」以外のなにものでもありませんね)。
そんなウェブ(テレビもか)のべらぼうさに比べれば、紙媒体の情報量不足はあきらかで、しかしそのペラペラを、なんだかんだと読ませてしまえる人を「編集者」と呼びたいと。
それは、Web2.0の無料経済全盛の時代に、(もちろん文字はタダですが)読むに堪えるテクストを生み出すには、コスト(金銭のことばかりではありません)も時間もかかることを知っている人のことです。
編集というプロセスにかかわる
「編集」ということばは、あたしの中では「過程 process」と同義語なのですが、その昔、あたしが『桃論』という奇怪なる本で、「編集」ということばを使ったら、苦情が来ましたよ。使い方がおかしいだろうと。
そしてこの立場でおこなう本書の問題提起とは、第一に、中小建設業と発注者が、「ソーシャル・キャピタル」の編集をすべきコミュニティの住人とは「だれなのか」ということです。これは、「公共工事の真の発注者とは誰か」という問題です。
そして第二には、「中小建設業のIT化」というときの「IT化」の捉え方が、例えば「ソーシャル・キャピタル」の編集作業とIT化の関係、というような表現をするように、多くの方々が考えているコンピュータ化や情報化、ましてやOA化とはぜんぜん違うものであるということです。(Lesson5 コミュニティ・ソリューション(3)―コミュニティ・ソリューションとソーシャル・キャピタル from 桃論―中小建設業IT化サバイバル論)
「編集」をこの意味で使うのは、つまりは「かかわる」ことの強調で、たとえば、インターネットであたしのテクストを読んだ人(個人的な編集者)が、なにを編集しているのか、といったとき、それが自分自身の個体化=「私」になろうとするプロセスであるのなら、そこに薄く「かかわる」ことを狙っているわけです。それは「街的」な〈世界〉の「呼び込み」としてです。
そのことは、紙媒体、つまりは雑誌でも同じであろうと思います。「かかわる」対象を〈消費〉中心に考えるなら、それは「みんな」を相手にしているだけでしかなく、「私」にも「われわれ」にもかかわれない。つまりはリージョナル性=パトリが欠如します。パトリなき編集はヘタレでしかなく、意味(サンス)が欠如した、意味作用の伝達でしかありません。
宣伝の意味作用(およびそれが引き起こす行動)はけっして個性的なものではなく、まったく示差的であり、限界的で組み合わせ的である。つまり、宣伝の意味作用は差異の作業的生産に由来している。この事実こそ消費のシステムを最も定義づけるものといえよう。(ジャン・ボードリヤール:『消費社会の神話と構造』:p112)
〈消費〉したい奴はすればいい
それでも、あたしらのやっていることは、ただ〈消費〉される(情報の消費という情報)でしかないこともある(というよりもその方が多い)のですが、「街的」(浅草的)は、簡単に消費されない強度ある時空です(店が勘違いしない限りですが)。だから、まずは入ってみなさいよと。そこが面白く感じられるなら、まだ人生は捨てたもんじゃないですよ、と(無責任に)呼び込みます。
そんなあたしは、〈消費〉については(〈消費〉を散々消費してきた者として)、ぶっちゃけどうでもよかったりしています。記号的消費でも、象徴的消費でも、誇示的消費(@ヴェブレン)でも好きにやってちょーだい、と思っています。簡単にいってしまえば、あたしの対〈消費〉戦略は、B29 VS 竹槍のようなものでしかありません。ただ被爆しない術はもっていると自負はしておりますが。
経済成長が日本の大人をダメにした。
あたしらはあまりにも過剰な時代に生きてしまったんだろうな、と思うのです。これは馬場宏二先生の受け売りですが、戦後の経済成長は、年率10%で30年続いたわけです。年率10%だと7年で倍になります。14年で4倍、21年で8倍、28年で16倍です。
こうなると28年間で1人当たりの生活水準は一桁上がってしまうわけで、28年で一桁上がるということは、子供の生活水準が、親が子供の頃の10倍以上になってしまっているということです。
子供の生活水準が一桁上がれば、親は子供になにも教えられない。親が知らないことを子供がやっているわけですから、今更、「ほれ、ベーゴマはこう回すんだよ」とか、小刀で鉛筆を削ってみせても尊敬されない。子供にとっては、そんなことは、今更どーでもいいことなんですね。
たまになんか聞いてきたかと思えば、TVゲームの画面に読めない漢字や横文字が出てきたときだけで、「とーちゃん、これなんてよむの?」、「それはどーゆーいみ?」。あたしゃ翻訳機じゃないのよと。(昭和ブームはこんな惨めなオヤジへの癒しに過ぎないのじゃないのかと云爾)。
つまり生活には、そしてその最小ユニットである「家族」には生活水準という断層があります。結局、親が子供に尊敬される(というか存在を認められる)のは、お金を与えるときぐらいのもので、それが親の唯一の機能になっていたりするなら、その結果、子供は「労働主体」ならぬ「消費主体」となって育ってしまうのでしょう。「労働主体」と「消費主体」の「生活」は違います。
労働主体/消費主体
労働主体は生きるために労働し、労働することが生きることですから、生きることに貪欲です。生きるために「われわれ」をみつけようとします。一方消費主体は〈消費〉するための労働はしないでしょう。〈消費〉は労働対価を悠々と超えます(クレジット、消費者金融、若しくはモラトリアム。エンコーは労働か?)。そこでは〈消費〉することが生きることである、が可能なのだと思います。
しかし「消費主体」には〈主体〉はないのであって、つまり「私」がない。その主体のなさの穴埋めに〈消費〉を続けるしかないものを「消費主体」と呼ぶのもへんなのですが、「消費主体」であった子供もやがては親となって子をもうける。そこでは〈消費〉の伝承しかないのですから、こうして主体のない「消費主体」は他ならぬ家族によって再生産されます。
これで文化継承はおじゃんです。世代に生まれた断層は埋めようがありません。「街的」もおじゃんになりかけています。浅草や岸和田には祭りがありますが、それは大人のハレの場で、そのハレを見せつける対象は、第一義的に子供でしょう(二義的には女性)。「どうだ、かっこいいだろう」と。そうしないと文化伝承はおじゃんなのです。
尊敬されない親父の通う酒場が、子供からどう見えるのかはわかりませんが、その行為が尊敬の対象とならないなら、バッキー井上さんの「あー」は、絶望的な「あー」になってしまう。
それで、子供からみたらなにをしているかわからない、つまりは尊敬されない仕事をしているあたしは、子供を酒場につれていって飯を食っていたりします。それは浅草的にはありだと思っていますが、世間一般(「みんな」)的には顰蹙もんでありましょう。「ソンケーされる父親とはそういう意味じゃないぞ」と。「じゃ、どんなんな意味なんだ。だれかおせーて頂戴!」とあたしはいいたい。
だからといって、経済成長至上主義を批判するのも今はしんどい。なにせ成長してませんからねぇ。たとえば自動車の無い時代にまで戻る、というような骨ある革命家はもう出ないでしょう。(あたしの知っている限りでは、西井一夫さんがそうでしたが、既に鬼籍の人です)。
しかし成長していないからいいのではなく、一旦失ったものはもう戻らない、ということが問題なのであって、つまりは「哲学」がなくなってしまった、それこそが問題なんでしょうね。
「街的」の哲学
「哲学」なんていいますと、なんともかび臭く、面倒臭いモノのようですが、「街的」の哲学とは、「銭儲け」の好きなあたしたちが、そればっかりでは種的に滅びてしまうので、進化的に利他的であるようにしつらえた外部装置のようなものです。いってみれば人類の進化上の智慧であって、それは「われわれ」の中で育てば、あれこれ考えなくても(その最も基本的な部分は)自然と身につくようにできていた。
「構造改革」なんていってた(いる)人たちは、だれもが当たり前にもっている「銭儲け」の欲動を、「街的」な哲学から開放しようとしていた(いる)わけですが、そんなことはいわれなくても、最初からあたしらは「銭儲け」は好きなのであって、それを今更に強調して見せるのは、下品であるばかりでなく、進化的にも破綻しているわけです。
なにしろそれで滅びるのは種であり、種からいずる個なのですから。おかげさんで、種である「街的」(「われわれ」)は、絶望的に衰退してしまいました。
個人的には、哲学=考えることは、「われわれ」の無かったあたしのビョーキのようなもので、「考える」ことは、あたしと〈他者〉を結ぶ補助線なんですよ。その補助線は、「みんな」を分断してみせる裂け目なのですが、つまりそれは、「私」になろうとするプロセスそのものです。
その補助線を自分で引くことができれば、受動は単なる「言いなり」ではなく、吉村道明の回転エビ固めのような、否定的受容という高度な技(?)も使えるようになるわけで、〈消費〉があたしを煽っても、煽られたふりして「あっかんべー」ができるのです。
だからその昔は、あたしの〈他者〉にも(無責任に)「考えろ!」といっていました。(なぜなら「街的」の哲学がなければ、自分で考えるしかないからです)。
しかし「あんたら、考えないと死ぬぞ!」と脅迫じみたこといをいってみても、みんな安楽死の方を選んでしまうわけで、それは、どう考えても「哲学」なんてものは直ぐに銭にはならないからだろうなと思うのです。
直ぐに銭にはならないものに興味を持てないのは、それは立ち位置が「交換」であるからで、つまりは「消費主体」とあんまりかわらない。逆に興味をもってくれるのは、そもそも考えている人か、もしくは「街的」のような実践的「哲学」の外部装置を持っている人(そしてそれが内部にあると感じる人)だけなのです。
つまり、ここでもほとんどおじゃんなのであり、楽な生き方としての〈消費者〉は再生産されます。つまりは「街的」なテクストを読むには才能が要る時代なんでしょう。それであたしは、どうにもこうにも面倒になりまして、そういう方々には「どうぞ、ご勝手に」なのでございます。(それは諦めを意味してはおりませんが)。
……と書き続けるこのテクストは、終わりがないのでございまして、「今回はこの辺で、では、ごきげんよう。」と書かないと終わりません。なので「今回はこの辺で、では、ごきげんよう。」と書くのですが、まぁ、締りがなくてすいません。
(編集中)
2008年03月18日 01:14
_1.jpg)
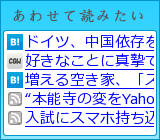
コメント
コメントを送ってください