いっつも消費者でおったら、しんどいやろ。
戸口も窓もない「バロックの館」。
京都精華大の「まちづくり論」の講義も2年目になりました。こないだも「モナドなわたしとまち」ということで、桃知が再三言及しているところの「バロックの館」をばーんと黒板に書いて説明しましたよ。これは学生にとっても「おー」という感じでめっちゃ分かりやすい。
私には戸口も窓もないのだが、それはまさしく〈実存すること〉によってなのであって、私の内にある伝達し得ない何らかの内容によるのではない。〈実存すること〉が伝達し得ないのは、〈実存すること〉が私の内にあってもっとも私的な(個人的な)ものである私の存在の中に根を張っているからである」(エマニュエル・レヴィナス『時間と他者』 「〈実存すること〉の孤独」)
単子(モナド)と同じように、そのような個体にはいわば「窓がない」。異なる個体同士を包摂して、そこにコミュニケーションを実現してくれるような、一切の安易な回路はそこにははじめから存在してはいない。このような個体性を、外延として表現してみれば、それはまさしく「点」にほかならない。このような点には、もちろんのこと窓とてなく、点と点を結びつける媒質も、想像界によらないかぎりは、現実(リアル)としてはない。(中沢新一『フィロソフィア・ヤポニカ』p321)
家族からも会社からも共同体性てものがなくなってしまった今、街は1階部分やないとあかん。街でいる「われわれ」にとっては、それが地元感覚というもので、いきつけの店やいつも通るストリートがあるから、そこに地元意識が生まれる。どこ生まれとか故郷とかそういうものではなしに、かつての「地域社会」に取って代われる「共同性」(われわれ)の可能性はあらかじめ街にしかない。
みんな同じことをやってる(シンクロ化)けれど、隣の人との関係性は全くないし、そこでは「われわれ」はなく「みんな」しかない。「パチンコ、パチンコ、パチンコにいくのさ。若しくは、集団的で一人ぽっちのみんな。」も京都の学生には抜群の講義ネタです。
そういうところから「〈私〉はいかにして〈私〉であるのか、〈個〉はいかにして〈個〉であるのか、そして私が他者とつながる(=コミュニケーションする)ということはどういうことか。」を考えること。この1年ほんまにそういうところから「街的」についてまた考えられるいい機会でした。
「都市計画」などという時点でもうあかん。
そっち系の「まちづくり論」のどうしようもなさは、結局、街を経済軸でしか見ることの出来ないしょうもなさで、人が何人行き来するのかとかそのうちF1層が何人とか、月坪あたりいくら売上があるのかとか、はたまた「都市計画」というやつでは、ランドマークをどこどうにつくって動線計画はこうだとか歴史的景観とかの議論で、そういうところに的外れさを感じているのでした。
どこまでも経済軸と市場経済合理性を具現化するためのハイパーインダストリアル的消費軸やと。
そうではなくて、どうして街によっては、昼間から酒を飲むことが罷り通るところとそうでないところがあるのかとか、そういうときは大通り沿いのカフェでなく横丁の居酒屋やお好み焼き屋を好むとか、わたしや桃知が大阪南部や浅草について毎日書いているアレですね。
わたしがこのかた大学でやっていることは、「交換/贈与」とか「消費と欲望」とか「店でのコミュニケーションのありよう」とかからネタで、引っ張りどころは例えばコンビニやファミレスやファーストフードやTSUTAYAでの「いらっしゃいませ、こんにちは」というマニュアル的挨拶のための挨拶とか、ケータイ電話やメールの登場によって、カフェや酒場などの都市空間が「着信を気にするところ」になってきていることです。
そしてどんどん街には「いまーここ」がリアルな実生活空間ではなくなってきていて、街的生活が消費空間に組み込まれてしまっている。
インターネットとケータイの登場は、都市の地理的・機能的ユビキタス化を進めてしまっていて、まるでカーナビみたいなことでしか捉えられない。街はすでに、ぐるなびみたいにケータイで「その時ーそこ」に送信されるための消費情報アーカイブなのか。この辺は桃知の専門分野なので、ぜひ見解を聞きたいところです。
いつも消費者は損するで。
おもしろいのは受講生に京都の寺町商店街の和菓子屋の娘とか、漢字を駆使して完璧に日本語の読み書きが出来るフランス人の学生とかがいて、かれらがいろいろレポートで書いてくれるところです。寺町商店街の和菓子屋の娘は「交換/贈与」の講義のあと、こういうことをレポートしてくれました。
私の商店街では、同じ商店街の人が買いに来ると、ときどき値引き、またはオマケをしてくれることがある。他にも、某店では同じ商店街の人が買いに来ると、Aランクの商品をBランクの値段で売ってくれるなどがある。別にこちらが値引きを頼んだわけでもなく、向も嫌々やっている訳でもない。けれどもこれが彼らの間では暗黙の了解のようになっているのは何故なのだろうと考えた。私の店でも、例えば同じ商店街の眼鏡屋が和菓子を買いに来ると値引きをし、次回、私が眼鏡を買いにあの眼鏡屋に行くと、値引きをしてくれる。ここで気付いたのが、「○○を買うならこの店」というのが決まっていることだった。つまり、値引きをするかわりに、○○を買うなら私の店を贔屓してほしいという、一種の契約だったのだ。ここまでの響きだけだと、裏で腹を探り合っているような、あまり良い印象を受けないかもしれない。しかしそれは商売上の作戦であり、同時にもっと大きなものが得られることを私は知っている。(中略)同じ商売人として、同じ町内の人間として、仲良くなることに越したことはない。またこうしたやり取りが商店街の雰囲気を明るくしているものだとも思う。
さすが京都の子、なかなか身体的というかするどいですな。フランスの学生はもっと切り込んでいて、「街場の消費活動」についてこんなことを書いてきている。
現代社会において、消費活動が、時間や場所などの外部の状況をものともせず、身勝手で、好きなときに、出来るようになった。(中略)フランスや他の国では、日曜日や休日に店が閉まっている。それだけで、人々は、暇な時間が出来ると、どうのように過ごせばよいか考えざるをえない状況におかれている。つまり、消費者以外の立場に立つのは、社会に強制的に進められている体験である。一方、日本や米国などでは、日曜日や休日になると、少しでも暇な時間が出来ると、毎日のように、当たり前に、買い物しに行くことは多い。日本では、「24時間・年中無休」と書いてある看板が多いが、よく考えると、店側だけでなく、市民側も、一日・一年中、消費者という立場に閉じこめられている。(中略)消費活動が増えるほど、個人の体験している人間関係が〈客対店員〉に限定されてしまう。したがって、相手の存在に対する認識の仕方も、単純化することになる。(中略)近年、その関係が強化されつつある。「モンスター○○」のさまざまな現象は、それの表れだと思う。
「生活の場である地元」では、実は町内会的な関係性があること、つまり「われわれ的消費者」としてはとても有利で、いつも「お客様は神様」であるデパートや大型ショッピングモール郊外的消費空間では「一人ぼっちのみんな的消費者」だから、そこではいつも損をしてると思うからクレーマーにならないとしょうがない。
客(消費者)と店(労働者あるいは生産者)というのはいつも可逆的であること。こんなこと町内会的な街では当然ですね。
例えばオフィスにいて、コピー機器でも何でもいいけれど、飛び込みのセールスが来たとする。その時に自分が、明日は逆の立場であることの可能性を考えないヤツはあんまりええことないでしょ。けれどもそういうヤツは、まるで犯罪者のようにセールスマンを追い返してしまう。
しかしこのあたりのメンタリティは街的な生活をしないとなかなかわからない。いつでもどこでも賢い消費者として自分を位置づけようとする悲劇については、結構多くの人が言ってない。これは私が言ってるのではなく、内田先生も生徒や学生の消費者化について、「そこが違うんだよとだれも言わない」と言っていることからも明らかですね。
人はまわりの人=われわれにとって、優しくておもろくて洒落ていて気持ちがよい、のが一番だということ。結局どこまでいってもあかんのが「消費者」やったりして。これ、こわいですな。
2008年12月13日 09:06
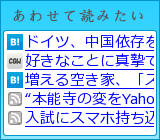
コメント
コメントを送ってください