しかしお好み焼き屋は、「街的」のかたまりみたいなもんやなあ。
アジールとしての店。
桃知と懇意にさせていただくようになったのは、『「街的」ということーお好み焼きは街の学校だ」を書いたことがきっかけでしたが、この新書は、会社を辞めてちょうどこの編集集団140Bを中島らと立ち上げたときに書いたものです。会社の定款をどうするかとか、登記手続きで法務局に行ったり、取引銀行をどこにするとか、そういうときに「街的ということ」とは何かを、身をよじりながら考えていたのです。
まだ大阪・中之島の事務所には何もなくて、神戸の家のiMacでしこしこと書いていました。そうしながらメシ+飲みで近所のお好み焼き屋によく行っていて、そこのお好み焼き屋で鉄板の上でテコを動かしながら、あるいはビールのグラスを上げ下げしながら、鉄板を挟んで週3回4回と、急によく行くようになって、その店の同じ世代のにいちゃんねえちゃんご夫婦に、いろいろと話しながら考えたことを家に帰って書いてました。
そのお好み焼き屋は場所柄、広域暴力団の組長クラスも来たりするところで、けれども普段来ている近所の学校の先生や90歳の父と60歳の娘親子とか、近くの魚屋や酒屋の大将や食べ盛りの高校生、その中にわたしがいるわけです。
けれども何がどうだということはない。芸能人がよく来る店とかの観点ではない(それより上か)。かれらは疑いようもなくそのコミュニティの一員であるからです。バッキー井上は「京都店特撰 その16 スコセッシやデ・ニーロがいつも描きたがっている下町のお好み焼き屋。「山本マンボ」の最後で、
犯罪発生率を下げるためには、下町のお好み焼き屋に助成金を出すことだ。
と書いていますが、ほんまにうまいこと言うなです。
山口組系の事務所がそれこそ点在している神戸という街、それも三宮や元町は、抗争の現場になることが多く、ホテルで宅見若頭が撃たれて死んだりしていますが、ことお好み焼き屋がそういうことに巻き込まれたという話は聞いたことがない。
お好み焼き屋で「タマ取った」というのは、どうなんでしょう、なんぼなんでも「それはないやろ」と思うのです。
街には商店街はなくなって、おーむちゃんの伊藤履物店はもうないけど、かろうじてお好み焼き屋は残っている。それは桃知がいうところの「アジール」そのものだからですね。お好み焼き屋ももちろん店なわけで交換経済の場所なんですが、それがほとんど前景化して見えてこない。
お好み焼き屋を書く肉体論。
わたしはお好み焼き屋については、岸和田の「かしみん」とかいろいろ書いてます。
オレの生まれ育った「だんじりの岸和田」もそうだが、関西のいいお好み焼き屋がある街というのは、通知簿1と5の親友がいて、毎日一緒にわいわいとやかましく遊べる街の奥行きがある。
それは、大阪の生野や神戸の長田や岸和田がどうの、という話では決してない。
このところ街の雑誌をやっていて、街が何だかつまらないと思える決定的な風景のひとつが年末だけによく売れる「関西1週間」のラブホテル情報付きのクリスマス特集や「HANAKOウエスト」のおいしい店選手権を見ながら、5千円ぐらいの仏ディナーを出すカフェみたいな内装の店で、メニューを一生懸命読み、シャンパンの銘柄を楽しそうに選んでるアベックとかグループが、どいつもこいつも通知簿3ばかりにしか見えないヤツらであることだ。
お好み焼きとその街のことを考えてるわけであるが、お好み焼きの旨さを人に語ったり、また書いたりすることは、オレの仕事の中でも「おいしいもの特集」的に記事を書いたり編集したりするのとは、全く違う行為だということを分かっている。
なぜなら、グルメ評論家とか美食ライターと言われる人のお好み焼きの記事は、仕事を依頼するに値しないほど退屈でシロウトっぽい、つまり街的にひとつもおもろない、ということを知っているからである。
オレの仕事は、街の雑誌「ミーツ」で、そこにご紹介するための店やその店の品書きつまり料理や酒といったネタを選び、それを写真や記事で表現することである。
けれどもその一見同じな一連の思考のプロセスが、ことお好み焼きに限っては感覚的に違ってくる。それは「どこでどんなお好み焼きに親しんできたか」という街的な個人史に直接リンクしてくるからだ。もちろんそこでは「いじめた泣かされた」「シバいたドツかれた」などとと同じレベルの、極めて具体性を持った肉体論が幅を利かせる。
ということ(『だんじり若頭日記』(晶文社)「岸和田の編集者ーお好み焼き屋の風景」に収録)です。考えてみれば、桃知も「ももちどぶろぐ」で浅草の「居酒屋浩司」を書き倒していたり、こないだは浩司でテレビにも出てましたけど(笑)、それは結局「消費者」的観点から店をデータ化して書く、ということではない、ということですね。「生活の事実性」はそこにはないから、そんなもの書いていて何がおもろいのだろう。
「生活の事実性」、それはメディア的「消費文化」ではなく、都市的「生活文化」に担保されたテキストであって、そこには「消費者である前に、われわれは街の実生活者である」という基底の諒解があります。桃知も「京都お好み焼き 吉野。なぜに京都でお好み焼きなのか。」で書いているけれど、「店に入るとお母さんから『イノウエくんのところからきたんか』と突然に言われた。」あの感覚です。
宮崎学さんは、こう書いている。
だからお好み焼き屋については、上手い書き手は見事に書いている。ちょっとここで編集者をやってみます。グルメライターは、消費そのものの対象としてのブランド名や、その際のデータしか書けないから、今や「使いもんにならん」とわたしが常々言ってるのも、よう分かると思います。
まず、宮崎学さん。この人は京都のヤクザ親分の息子で「近代ヤクザ論」など独特の本を書いていますね。こないだも宮崎さんと門倉貴史(経済学者「反米経済」の著者)の出たばかりの新書『大恐慌を生き残るアウトロー経済入門』読んでたら、今回の金融恐慌の根源は、ハイリスク・ハイリターンを生むレバレッジだと言うてました。でもって、株や債券市場は実体経済を反映していない。そこのことを宮崎さんは、
宮 例えば債券先物取引では証拠金比率1%で取引をする場合、投資家は100万円の元本で、1億円の債券を買うことが出来ますね。すると額面100万円の債券価格が1円変動すると、100万円の損益が生まれる。つまり100万円の元手が1日で倍になったり、ゼロになったりするんですね。
これはまさに賭場、カジノの思想なんですよ。今はカネがないからやらないけど、昔は私も大阪・西成あたりの賭場へよく行っていました。そこでは100万円を持っていくと、1000万円の勝負をさせてくれるんです。
もちろん負け続けるから、持ってきた100万円以上のすごい損出を出してとぼとぼと帰るんだけども(笑)、帰り道の街のなかでは「うどん200円」とかそういう現実社会なんです。もちろん、こっちはそのうどんを食べるカネも残っていないんだけど、ついさっきまで100万単位のカネをやり取りしていたのに、一歩外へ出たら…とね。実体経済と投機マネーの乖離をカラダでかんじていたなあ、あの頃は(笑)。
門 (笑)。アメリカの下院議員で金融安定化案がいったんは否決されたのは、ウォール街にはこのカジノ経済で儲けた金融関係者がいっぱいいることをアメリカ国民がしっているからでしょう。
「経済至上主義」とか「消費文化」とかの世界とは身体論が違います。これは、笑てしまいますね。が、ちょっと小賢しいだけでカネを扱ってきた現代アメリカ人的な子どもが、ヤクザ顔負けのことをやってるから怖い。えーと、お好み焼きでしたね。
祇園や宮川町にいる男や女は水商売の人間、京都風に言えば花街衆である。この連中は良くも悪しくもプロであった。なかでも、プロ中のプロはお茶屋や置屋のおばちゃん連中だった。
(中略)
こんなことが縁で、祇園や宮川町のおばちゃん達との付き合いが始まったわけだ。
「おばちゃん、起きとるか? お好み焼き食いに行くぞ」
昼過ぎ頃、お茶屋や自宅で寝ているおばちゃんたちを誘いに行く。
(中略)
誘いに行くと、いずれも京都の最底辺の出身でお好み焼きなど俗な食物に目のないおばちゃんたちが五、六人起き抜けの顔で喜んでついてくる。ついでに、木屋町の裏手に群がり住んでいるオカマ連中も連れて行く。遣り手婆とオカマが大勢お好み焼きを頬ばりながら得意の話術を展開するのだから、面白くないわけがない。居合わせた客や店員が笑い転げていた。
こんな内輪の場だから話はアケスケで、昨夜自民党の有力議員が芸妓のだれだれに派手に袖にされたとか、大企業のオーナーが芸妓に子供を産ませたとか、生々しい話題に及ぶこともある。
(中略)
お好み焼きのコテを振りたてながら、「羽振りはええらしいけど、養子やから金は奥方に握られとるんと違うか」「それはないようや、自前の金もだいぶあるらしいで」などと情報を持ちより、仔細に検討する。そのうえで、旦那から「長く細く」金を引き出すか、「太く短く」金をむしり取るかを決める。(中略)
後に企業恐喝容疑で京都府警から指名手配をくらったとき、このおばちゃんたちから「祇園か宮川町に隠れなはれ。わてらが全部面倒見るから」という連絡が入った。こういう徹底した身贔屓の世界で生きている人間たちなのである。
(中略)
京都府警に留置されているときも、祇園のオカマがおばちゃんの名代として差し入れにきた。おばちゃんたちとよく行った店のコーヒーとお好み焼きだった。
『 突破者(上)』(幻冬舎アウトロー文庫)332-335P
ここに書かれているのは場所ですね。見事にお好み焼きそのものについては出てこない。街場の細民たちの「アジール」というのはこういう匂いというか手触りがありますね。
許永中のお好み焼き屋。
次は森功さんの出たばかりの『許永中 日本の闇を背負い続けた男』から。獄中の許と何回も面談し往復書簡を交わしたあと、許が生まれ育った大阪市北区中津のお好み焼き屋を取材している。
許永中は数千億円という桁違いの金を動かすようになってからも、側近たちを引き連れ、しばしなこの中津を訪れた。
中津には道幅三メートルぐらいの古い商店街があり、年老いた魚屋や八百屋の女将が細々と営業している。前述した古い木造長屋は、その周囲に固まっていた。書店街から脇にそれ、さらに入り組んだ狭い路地を入った長屋の外れに、小さなお好み焼き屋がある。
裕福になった後にも、許はこの店に焼きそばを食べるために訪れた。仕事の合間、暇を見つけては、事務所から社員を連れ、わざわざ黒い大型ベンツでお好み焼き屋へ出かけたという。狭い路地に入って、昔通った馴染みの店に横付けにし、大きな身体をかがめて暖簾をくぐった。
「ここの焼きそばが最高なんや」
焼きそばをつまみにし、ビールをコップであおる。そうして、幹部社員を前にして幼いころを懐かしんだ。しばしば高級なダークスーツに身を包んで、このお好み焼き屋に立ち寄ったという。
中津には、件のお好み焼き屋はまだあった。うっかりすると、見落としそうな入り口。玄関は一間ほどの狭い間口しかなく、アルミサッシの引き戸になっている。引き戸を開けて店のなかに入っていった。店内もかなり窮屈だ。細長い鉄板の前に、丸いスティール製のパイプ椅子がいくつか置かれている。これだと、客が一〇人も入れば、すし詰め状態になるだろう。
もとは戦争未亡人が店を始めたという。私が訪れたのは二〇〇一(平成一三)年だが、このときすでにこの女主人は九〇歳を超えていた。店では未亡人の娘が、焼きそばやお好み焼きを焼いていた。聞くと、中津小学校出身だという。年齢が許より二つ上だというから、六〇歳少し前。しばらくすると、店主の母親が出てきた。
「この店を始めてから、もう四五年以上になるんですわ。私は永中さんのお母さんと同じ歳ですねん。前は夜も店を開けててな。近くの会社勤めの人が仕事帰りに来て、飲んでいってくれましたけど、いまは夕方六時には店を閉めますねん」
九〇歳を超える女主人は、まだまだ元気で店に顔を出しているという。さっそく焼きそばを注文する。許のいうとおり、その味は格別だった。
「焼きそばもお好み焼きも、昔と変わってませんねん。味はそのまんま。永中さんは子どものころからよく来てくれはって、あのころはお好み一枚五〇円でしたんや。いまは五〇〇円。ちょっと前まで永中さんも来てはりましたけど、このところは無理ですわな。でも、尾崎さんなんか、いまでもよく来てくれますで」
年齢を感じさせないほど元気である。
「お母さんも、前は隣町の中崎町から車に乗って来てました。永中さんが建てはった家に住んでましてね、お母さんにも運転手がついてましてな。最近また中津に移ってこられて、ひとりで歩いて来てます。娘さんが一人歩きは危ないいうて止めるそうで、こっそり来るんです。よく(大阪北部の)箕面の風呂(温泉)へ行こうと誘われます。去年の一二月にも来て、そういってはりましたな」
許にとって、中津は生涯忘れられない大切な場所である。
『許永中 日本の闇を背負い続けた男』(講談社) 39-41p
街場から成り上がっていったこの世界の人も、自分が育った街そのものが、実人生が垣間見えるそのものとして、一軒のお好み焼き屋に投影されている。
鷲田せんせも「山本マンボ」。
続いて阪大総長の鷲田清一せんせ。この現代日本を代表する哲学者は、こういうお好み焼き屋を書いている。
町内ごとに仕出し屋があり、お好み焼屋があるといえばちょっとおおげさになるが、とにかくよく食べた。幼いときはテレビの探偵ドラマを観せてもらいにうどん屋に、十歳頃は遊び帰りに公園の屋台に、高校のときは放課後の腹癒しに繁華街の二階の粗末な店に、足を運んだ。高校生のカップルが多く、コテをもってケーキの入刀よりはるか前の「共同作業」をおこなっていた。
ただし、このお好み焼、大阪のような混ぜ焼とは異なる。京都のひとは「べた焼」と言うのだが、メリケン粉を溶いたものを極薄に鉄板に引き、鰹節をぱあっと散らしたあと具をいろいろのせて、さらにその上から具に染みいるようにメリケン粉の溶き汁を垂らす、あの焼き方である。具といってもそんなにたいそうなものではなく(「デラックス」とか「モダン」という羞ずかしい言葉はだれも口にしなかった)、ほんのわずかな削り節と数本のキャベツと中華麺以外はほとんどメリケン粉と水だけ、これに激辛のどろソースをかけた薄い薄い「べた焼き」を、小学校のとき児童公園のうらぶれた屋台で、デパートの「お子様ランチ」と拮抗するものとしてむさぼり食った。友だちと賭をして、十三枚平らげたこともある。親からは小銭しかもたせてもらえず、心細い想いで口に運んだので、枚数はよく憶えている。
(中略)
塩小路高倉下がる東側、JRを渡る車道のたもとにその店はある。
入店するや、「飲みもんはケースのなか、自動販売機とおんなじ値段、水はセルフサービス!」と、「嫁はん」から威勢のよい言葉を浴びせられる。メニューは、まんぼ焼と、焼きそばと、お好み焼と、ホルモン焼だけ。あとは、油カス、肉、ねぎ、イカ、ホルモン、玉子といったトッピングで差異化する。ベースはメリケン粉を溶いたのに、紅ショウガ、天かす、油カス、ねぎ少し、刻んだおこうこ(東でいうおしんこ)、そして鰹節の粉。無理言って、そのベーシックを、「なんもなし」というふうに頼むと、「ほんならお金とれへんやん」と反撃がくる。あきらめて、「そしたら豚と海老と……」としょぼしょぼ答える。
開業五十六年、鉄板は二代目、二センチ近くある。火は炭と練炭。ご主人は六十六歳(らしい)、奥方はどう見ても娘のように見える。「夫婦?」
「さあ」
「ややこしそうな関係やなあ」
「どうでもええねん」
「娘さんやろか」
「ワーォ」残念ながら、店は朝十時から夕方の四時四十五分までしかやっていない。理由を聞けば、「からだもたへんもん」
こんな会話をできるような歳になったんやなあ、とあらためておもう。
(中略)
放課後、児童公園で仲間と大暴れしたあと、公園の隅にある屋台に集い、鉄板のまわりに立ってコテで「ベた焼き」を食べるのが、なにより愉しみだった。
(中略)
食べているあいだじゅう、ほとんど口をきかないぼくらに、おばちゃんは、たまにはぼそっと、学校のことではなく、どうでもいいようなことを訊いた。母親に答えるように、わずかな言葉をつっけんどんに返した。そしてまた沈黙。せいぜい十五分ほどの幸福。
このおばちゃんがぼくのためにからだを動かしてくれるのを、見たかったのかもしれない。作ってもらっているという気分が、たぶん味のほとんどを占めていた。
(中略)
「ものの味わいの判る人は人情も判るのではないかと思いやす」と言った料理人がかつていた。じぶんのために働いてくれるひとへの想いがないと、味は判らないというわけだ。味というものの在り処を考えるとき、これはなかなか身に沁みる話ではある。少なくとも、味蕾の仕組みについての「科学的」議論よりははるかにこころに響く。レストランの洋食、ホテルの中華料理、料亭の懐石料理はきらいだ。厨房から切り離されているから。だれかがわたしのために作ってくれている……というシチュエーションに弱いのだろう。
『京都の平熱』 (講談社) 19-27p
ここに出てくる「今の話」の店はバッキー井上の書いている「山本まんぼ」のことであって、わたしはこれを鷲田せんせの著作で発見したときに、鳥肌が立ちましたよ。
ここでさまざまな著者とその文章の書かれた背景を解説するのは、えーと文芸評論家の領域なので、わたしは編集者なのでやめときますが、
そして彼は、それを思考的闘争として、(なにげに)『「街的」ということ』で、われわれにしかけてきた。「お前らの街にこれはあるか」、と。だから私は、「浅草にはある」と答えた。http://www.momoti.com/blog/2006/12/post_346.html
という人が、まだこの世の中にいて同じ時間を過ごしている、と思えるから、人生捨てたものじゃないと思うのです。
2009年02月24日 22:30
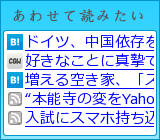
コメント
コメントを送ってください