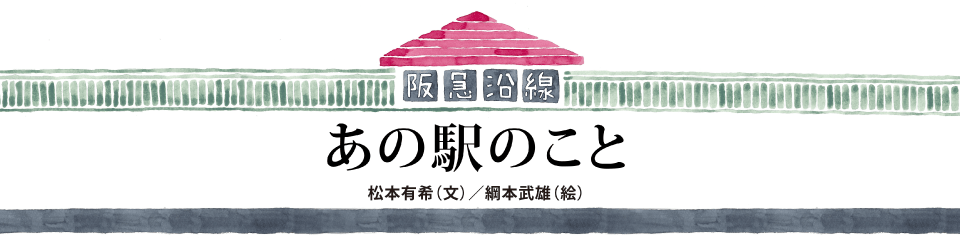2022年秋、阪急塚口駅前が激変した。1978年に開業した駅前の商業施設「塚口さんさんタウン」にあった、のどかな昭和のランドマーク・屋上観覧車が姿を消してから久しいが、ついに3番館が取り壊されて、ピカピカの商業施設[SOCOLA塚口クロス]を含む16階の高層マンションに生まれ変わった。新旧のコントラストが強くなり、駅前の風景は一変し、周辺住民の暮らしも変わっただろう。TOKK連載時の『阪急沿線 ちょい駅散歩』(2008〜16)で描いた観覧車が、誰かの記憶に留まるといいが、街はどんどん変わっていく。まるで生き物のように、世代交代を繰り返し、姿を変え続ける。
まだ建て替えられていない1番館の地下に、映画を愛するファンが全国から訪れる聖地[塚口サンサン劇場]がある。学生の頃にここで映画を観た時は、梅田や三宮の大規模館とは違って、ガラガラでちょっと薄暗い映画館だったのに、いつの間に変貌を遂げたのか。きっかけは、シネコンの台頭により客足が遠のきかけていた2011年頃。映画の魅力をお客さんと分かち合い、楽しみ尽くす企画が、映画愛あふれるスタッフの創意工夫によって数々生み出され、お客さんも巻き込んで話題を呼び、奇跡の復活を遂げたのだ。
常識破りの復活劇は、中心となった名物社員・戸村文彦さんによる著書『まちの映画館 踊るマサラシネマ』(西日本出版社)に綴られているので、“塚口の奇跡”を知りたい人は、ぜひ読んでみてほしい。「他ではなく、ここで映画を観たい」と言わせる、サービス精神と遊び心満点の歩みは、映画化にもってこい。いつか自画自賛上映がかなうかもしれない。
街場の美味いもんトライアングル
歩いていたらお昼どきだったので、塚口さんさんタウン2号館に君臨するカレーの名店[アングル]へ。しっかりと大鍋で煮込まれたカレーを求めて、遠方からもファンが足を運ぶ。メニューを眺めて「説明不要! アングル最高傑作」のフレーズに、「特選和牛カレー」1,500円を注文。
厨房を囲むU字カウンターに座って待っている間、古い記憶が浮かんできた。アングルは、学生時代に付き合っていた人のアルバイト先だった。留学が決まってアルバイトを辞める彼に、激励金としてボーナスをくれた店長。感動して泣いていたあの人は元気かなぁ。そんなことを考えていると、目の前に真っ白なお皿に盛られた白米と、銀色のカレーポットが到着。ゴロゴロと大きい牛肉は口の中でほどける柔らかさ。綱本さんはもう一つの看板メニュー「ポークしめじ」を美味しそうに平らげた。
聞けば、カレールーに使うダシを取るためだけに、毎月1トン以上も牛バラ肉を使うという。そして帰り際、勝手口から見えた山積みのタマネギとよつ葉バターも、甘みが出るまで炒めてルーに。人を惹きつけてやまないカレーは、想像を超える手間暇をかけて、生まれているのだ。
アングルから数歩先の[スパゲティ専門店 タント]と[ピザ マーレ]はアングルの姉妹店。タントは「ベーコンなすスパゲティ」発祥の店だし、TOKKで取材させてもらったこともある。しかもディナータイムには、どの店からも3店のメニューを注文できるという! 実直に美味しいものを作り続けているこんなシェフたちの店こそ、街の宝だと私は思う。
鏡開きは塚口の職人技あってのもの
お腹も心も満たされて、塚口駅の北側へと出発。ほどなく、立派な庭付きの日本家屋が見えてきて、[株式会社岸本吉二商店]に到着。鏡開きでおなじみの「菰樽(こもだる)」を作る、今では全国で3社しかない貴重な存在だ(うち2社は尼崎市内にある)。白鶴・大関・剣菱・菊正宗・月桂冠・黄桜と、灘・伏見の有名どころの酒蔵が取引先に名を連ねる。
江戸時代から尼崎では、農家がつくる菰縄(こもなわ)を買い取って、伊丹や灘の蔵元に納める商売があった。今は住宅街だが、昔は田園地帯が広がり、酒処への地の利の良さからそういった商いが生まれたのだろう。岸本吉二商店は明治33年(1900)に創業し、今では全国の神社に奉納されている酒樽の半数以上を手掛けるようになった。
綱本さんは、長く尼崎の産業振興にも関わっていて、そのご縁で同社のパンフレットを制作。TOKK『ちょい駅散歩』で塚口の取材先を探す際、綱本さんからこのパンフレットを見せてもらい、美しく描き込まれた菰樽や躍動感ある職人の絵に引き込まれたことを覚えている。菰樽の制作工房にお邪魔して、酒樽に菰を巻いていく荷師の手際の良さに圧倒された。鏡開きは日本が誇る「お祝い文化」の象徴だ。関係者で木槌を持って酒樽を囲み、ヨイショ!の掛け声と共に勢いよく蓋を叩き割る様子は、なんとも晴れがましい。同社では家庭でも楽しめるミニサイズの菰樽も販売されていて、文化の継承に一役買っている。
大資本が勝てない「商店街」の素敵キャラ
阪急伊丹線沿いを少し歩いて、真っ直ぐに走る阪急電車の線路を眺めつつ、塚口商店街へ。「塚口笑店街」と名乗り、キャッチコピーは「笑える今日がここにある」。地元の憩いの場たらんと、個性豊かな店主たちが知恵を出し合い、盛り上げる元気な商店街だ。その中心に「私、商店街のマスコットガールやねん」と笑いつつ、実はめっちゃよく働く副理事長がいた。[アリクイ食堂]の店長・吉井佳子さんだ。同店は、すべて手作りのお惣菜がおいしい家庭料理店&カフェで、吉井さんが27歳でオープン。以来、移転を挟んで10年以上ファンの胃袋を掴み、塚口駅北改札口のマクドの角を曲がってすぐの場所で、昼も夜も料理を作り続けている。
実は彼女、私がTOKK編集部に入る前に、宣伝会議主宰の「編集・ライター養成講座」で学んでいた時の同級生。お互い20代で夢をもって、書いて、遊んでいた良き時代。幼い頃から漠然と「書く仕事につきたい」と思っていたが、就職氷河期もあり出版・新聞系の就職は完敗。システム会社に入社した私は3年目、「このままでいいのかな」と思っていた。たまたま書店で手にとった『編集会議』という雑誌で、講座を目にして興奮し、勢いで申し込んだのが、人生の転機となった。そこで学ぶ日々は、私にとって発見の連続。同じテーマで書いても、書き手によって全く違う文章が生まれる。自分の文章の持ち味やクセも思い知った。何より「書くことが好き」な仲間にめぐりあえたことが、一番楽しかった。
吉井さんは当時から人が大好きで、年の差を屁とも思わないキャラで、かつ人情にあつくて優しい人。今の「食堂のおかみさん」は彼女にぴったりだし、塚口商店街で生まれた「おかもち屋台(Uber Eatsの走りのようなイベント)」から「地元商店街の味を集めた冷凍自販機」まで、人をつないでアイデアを一緒に練り、盛り立ててきた。いつも「もう休みたい〜」と言いながら、人の世話を焼き、自分の店を切り盛りする彼女みたいな人が、この商店街にはたくさんいる。地元を愛し、ゆるくつながって、無理せずできる範囲で、お客さんの笑顔のためにちょっと頑張る。そんな思いで、居心地のいい「街」はできている。