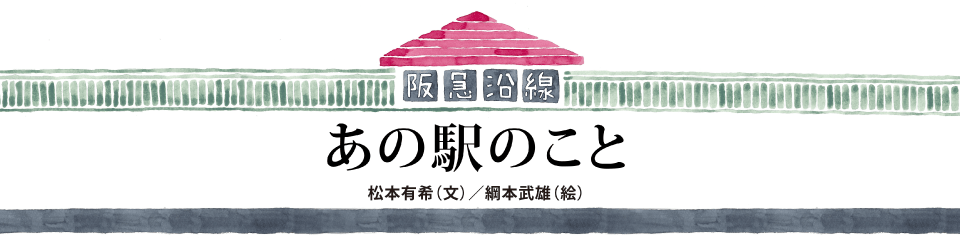阪急甲陽線の始発駅と終着駅の間に一つだけある苦楽園口駅は、大正13年(1924)の開業時は「越木岩(こしきいわ)信号所」だったが、翌年、駅に昇格した。駅の東にある苦楽園口橋から北を見れば、ポコンとお椀を伏せたような甲山(かぶとやま)が鎮座する。のどかで品のある駅前を眺めて、深呼吸して歩き出す。
東へ10分も歩くと見えてくるのは、広い空を映すニテコ池。北から上池・中池・下池と3段に分かれた貯水池で、「西宮市所管の近代水道関連遺産」として、2008年に経済産業省の「近代化産業遺産」にも登録されている。池畔を囲む桜並木、絵になるフォルムの取水塔、気ままに過ごす水鳥たち。心安らぐ風景に、肩の力が抜けていく。
日本にあるカタカナの地名には、なぜか興味をそそられる。「ニテコ」の由来を調べてみれば、“えべっさん” の西宮神社との浅からぬ縁があるらしい。福男選びで知られる1月10日「開門神事」の舞台・赤門の左右に連なる「大練塀(おおねりべい)」は、室町時代に造られた現存最古の築地塀だ。練った土を突き固めて造るため、良質な採土場だったこの地の土を人夫が運ぶ「ネッテコイ、ネッテコイ(練ってこい)」という掛け声が訛って、「ニテコ」となったのだという。その後、採土場跡に水が溜まって誕生した池がニテコ池だ。
ニテコ池の西側丘陵地は、戦前から高級住宅地として開発され、旧日本銀行大阪支店長や、住友グループ最後の総帥・古田俊之助、住友銀行社長・岡橋林(しげる)、岩井商店店主・岩井豊治ら、関西財界の重鎮が住まいを構えた。中でも、この地をこよなく愛したのが「経営の神様」と呼ばれる、パナソニックグループ創業者・松下幸之助(1894〜1989)であった。
幸之助は、下池西側の広大な土地を求め、昭和12年(1937)から足掛け3年もの年月をかけ、「光雲荘」を建設。書院造りに西洋建築を取り入れた大邸宅で、「300年後も日本建築の参考となるように」と、当時最高の建築技術を集めて造られた。松下家の客人や取引先をもてなす迎賓館としても使われ、家族ぐるみでもてなしたという。
幸之助が綴った『光雲荘雑記』には、こんな一節がある。
ながめてあきぬ雲の流れ、味わってつきせぬ人の世のさだめ、
そんなことを私は光雲荘の庭に立ってシミジミと考えるのである。
当時のまま残る正門前に立ち、見事な松を見上げれば、社業を通して日本を良くするために、この地で思索を深めた幸之助の姿が、輪郭をもって立ち上がってくる(現在、建物は枚方市のパナソニックグループの研修施設に移設されている)。
そして、上池西側にはもう一つ「名次庵(なつぎあん)」という、幸之助が戦後に建てた家がある。ニテコ池から1本西側の道沿いに、表札が今も確認できる。妻・むめのとの暮らしは、松下家最後の執事だった高橋誠之助が書いた『神様の女房』(ダイヤモンド社)で垣間見える。
むめのは、仕事に出かける夫を、玄関ではなく、急な階段を降りた門の外まで、夏も冬も毎日見送ったという。
晩年には、ニテコ池の周りを夫婦でよく散歩した。夫が仕事に邁進できるよう支えた妻と、妻に感謝を欠かさなかった夫。大企業を一から築き上げた、激動の人生を二人三脚で駆けた二人にとって、誰にも邪魔されずに語らいながらそぞろ歩くのは、心が満たされた時間だったに違いない。
戦災の悲話と、震災の鎮魂と
太平洋戦争が始まると、ニテコ池は華やかな暮らしとは対照的なエピソードの舞台となる。実はニテコ池は、野坂昭如氏の自伝的小説『火垂(ほた)るの墓』(新潮文庫)で、清太と節子が暮らした防空壕があった場所なのだ。太平洋戦争末期、家族らしい暮らしを守ろうとした14歳と4歳の兄妹。サクマ式ドロップスの缶を宝物にしていた節子の笑顔、蚊帳の中で二人を照らす蛍の光、妹を荼毘に付した煙を見つめる清太の虚ろな目。スタジオジブリのアニメ映画のシーンに、どうしても我が子を重ねてしまう。
私の子供も兄と妹。もし戦争になったら、両親がいなくなったら。親目線でのリアルな想像ができるようになった分、昔よりも清太と節子の物語が胸に迫り、涙なくしては見られなくなった。
隣接する西宮震災記念碑公園に、「小説 火垂るの墓 誕生の地」という文学記念碑があるので訪れた。ニテコ池のある満池谷(まんちだに)町に住む土屋純男さんが、小説の足跡が残る地元を郷土史家と共に調査するうち、野坂作品の顕彰と平和を願う記念碑の建立を目指して2017年から募金活動をスタート。約790万円が寄せられ、記念碑は2020年5月に除幕式を迎えた。アニメ映画のワンシーンも描かれた石碑には、阪急甲陽園駅の北にある[アンネのバラの教会]から贈られた、鎮魂と平和を願うバラがそっと寄り添う。
この公園には、阪神・淡路大震災で亡くなった西宮市関係者1,086人の名前を刻銘した追悼碑がある。震災被害写真のカラー陶板と共に、リアルな被災を伝えている。この連載の取材で阪急仁川駅から歩いて訪れた、仁川百合野町の地すべり被害も同じ西宮市なので、ここで記録を見ることができる。
どの石碑も陶板も細工が見事なので、調べてみたら、すぐ近くの中谷石材工業所が製作を担当したという。見ごたえのある記念碑を造ることで、たくさんの人が訪れ、戦争や震災の記憶を風化させずに伝えていける。そんな石工職人たちの気合いの入った仕事に感じられた。
『火垂るの墓』ゆかりの場所を歩いてめぐる歴史ウォークなども行われ、地域の歴史を伝える試みが続けられている。
年に一度だけ開放される、桜の園
西宮市の市花は、桜。そのゆかりは西宮震災記念碑公園に隣接する、越水(こしみず)浄水場にある。浄水場完成の翌年、大正13年(1924)に、有志が100本あまりの桜の木を寄付したことが始まり。その後、桜博士として知られる笹部新太郎(1887〜1978)が、ヤマザクラなどの日本固有の桜を中心に移植し、地元の人たちの手で大切に育てられてきた。
越水浄水場は、毎年期間限定で「さくらの通り抜け」として一般公開され、夙川の桜並木に勝るとも劣らない見事な桜が楽しめる。阪急沿線のおでかけ情報誌『TOKK』の取材で平日に訪れ、静かな浄水場内を歩き、仕事を忘れて春を満喫していたら、突然のゲリラ豪雨に降られて、途方に暮れた思い出がある。
ちなみに、市花が桜ということで、阪急甲陽園駅の北にある「北山緑化植物園」内には、西宮市植物生産研究センターがあり、市オリジナル品種を開発・育成しているという。「宮の雛桜」「今津紅寒桜」「越水早咲き」「夙川舞桜」「西宮権現平桜」の5種があり、いずれも西宮ゆかりの雅な名前が付けられている。
さて気づけばお昼どき。一度苦楽園口橋に戻り、たもとに佇む[大正庵 苦楽園口駅前店]で遅めの昼食をいただくことにした。大きな赤い提灯が目印で、昔は普通の蕎麦・和食店だったように思うが、何かが違う。店先の黒板には「マラバール風シュリンプカレー」に「燻製5種盛」?? 明らかに変わっている。
店長に聞けば、2019年5月に40年の歴史を閉じたが、閉店を惜しんだ現オーナーが店を引き継いだという。「食のドン・キホーテ」を目指し、おいしい食べ物と飲み物を幅広く揃える、使い勝手のいい店にチェンジ。メニューには、蕎麦はもちろん、ラーメン、カレー、一品料理も充実し、クラフトビールから焼酎、入手困難な日本酒までずらり。多彩なメニューを調理できる理由は、店員一人ひとりの得意料理を活かしているから。今は魚を扱うのに長けた人がいるので、「炙りサーモンの親子丼」がおすすめとのこと。お花見の特等席として桜の時期は特に混み合うが、普段は「ちょっと呑めて、みんなで食事できるお店」として、地元の人に愛されている。
注文した「シュリンプカレー」はスパイスをしっかり利かせつつマイルドで食べやすく、燻製をおつまみに、画家の綱本さんとお昼からつい一杯飲んでしまった。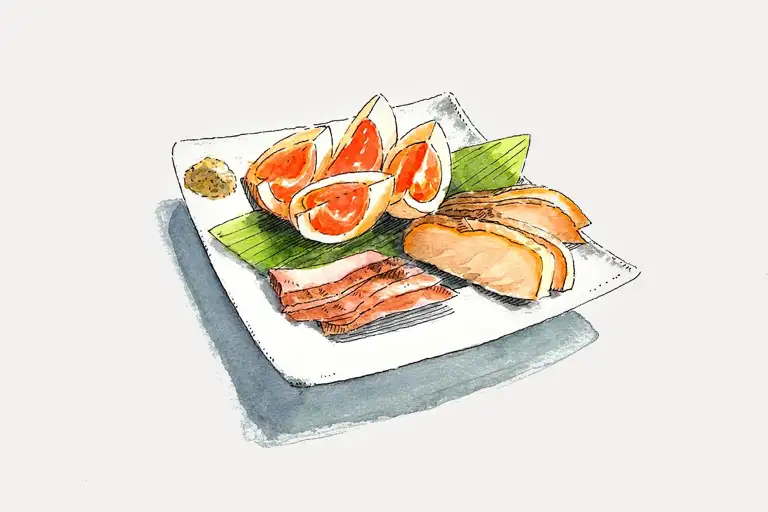
夙川沿いの窓からは、桜、紫陽花、紅葉と、まるで絵巻物のように移ろう季節が楽しめる。目の前の川辺で友人たちと夜桜見物をした若い頃の思い出が浮かぶ。自由で、取り留めもない話を延々とした日々。燻製とビールが染みる歳になったものだ。