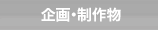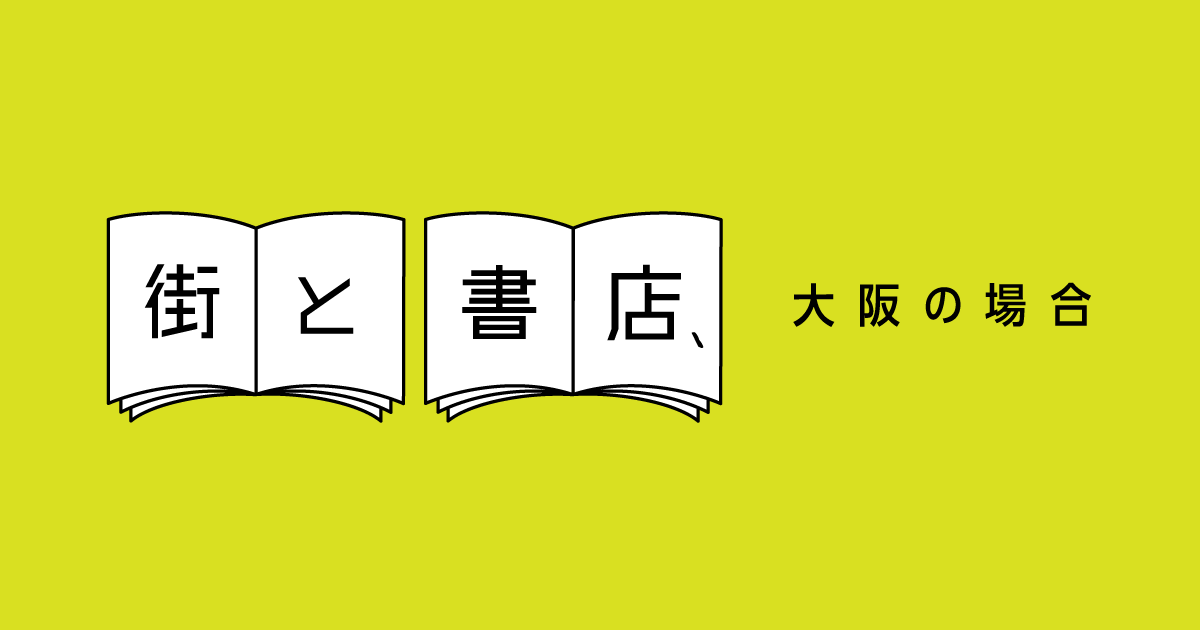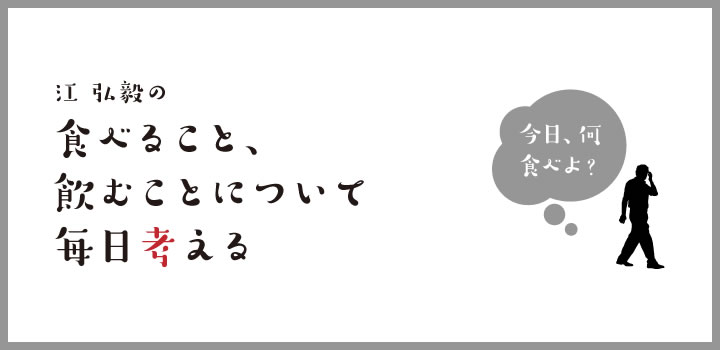前回、[バー・ウイスキー]のときに、「酒場ライター」バッキー井上のことを書いて、
「酒場ライター」があるとしたら「酒場フォトグラファー」というのもアリちゃうか、などと考えてしまったのである。
しかし、この日この夜でやめた。
理由はまた次の機会にでも。
と書いたら、多くの人から「ナンで、酒場フォトグラファーはやらないんですか」という声が届いた。
「早く書きなさい」ということである。
とくに新連載が始まって、昨日2回目の原稿を入れたばかりの『あまから手帖』の安藤副編集長などは、ほんま急かす急かす。
それについて書く。
その前にまず、酒場ライターについて違う話をば。
酒場の記事の難しくもおもろいところは、「人間は変容する」というところに軸足を置かないとつまらないからだ。極端に言うと、下戸や素面では書けない、ということになる。
つまり、酒は酔うから酒なのであって、それによって「人間は変容」する。その変容の仕方の記述こそ「書くこと」、今流でいうところのコンテンツなのだろう。
たとえば[堂島サンボア]のビールはとてもうまい。書けば、キリンのラガー小瓶で600円、鍵澤秀都さんが栓を抜いてグラスに注いで客に出す。
その同じラガーがどうしてコンビニの205円(税別)の缶と違うのか。それに加えて大瓶で600円の行きつけのお好み焼き屋のそれと、足の綺麗な別嬪がいる北新地のラウンジの2000円の小瓶と、中身が同じラガーなのに値段がこうも違うのはなぜか。
そんなことを言い出すと、それは「付加価値なんです」などといったしょぼくて眠たい答えが返ってきたり、「そんなのは個人の価値観だから、どうでもいいんじゃないの(アホかおまえは)」といったクールな返答がされたりするが、そういう発想こそが鈍臭いのである。
人間は変容する。味覚も当然変容するのだ。
堂島のサンボアのビールは、同じ中身でも家で飲むビールよりもうまいのだ。同様に北新地のラウンジ云々のビールも、また違った味がする。
こんなのは誰もが知っている。けれどもそういうことを言うのはナシなのである。何でか知らんけど。
養老孟司先生と一度、ご一緒に飲む機会があって、その時教わったのは、「人はいつでも変わる。同じ自分なんていない」ということだ。
わたしは「そらそうやな」などと思ってたが、その後、『読まない力』という新書を読んでいたら、いきなり「まえがき」でそのあたりについて執拗に書かれていた。
読んで一気にわかった。つまりその時、まだまだオレは考えが浅かった。
情報とは「時間が経っても変化しないもの」を指す。そんな定義は学校では教えてくれない。じつは私が勝手に定義した。でもそれで十分だと思っている。写真の自分は、いつまで経っても歳をとらない。情報だからである。学校から成績証明書を取り寄せると、若い頃より知恵がついているはずなのに、いつでも同じ成績が返ってくる。情報だからである。血圧が一四〇などといっているが、測ってみれば、うっかりすると毎回違うとわかるはずである。測ったときの血圧がたまたま一四〇だったのである。
養老先生独壇場の語り口である。
情報化社会というのは「私は私、同じ私」という自我とか自己とかを措定したうえでの「脳化社会」、つまり「意識のみ」を扱う社会のことだ。もちろん人間は意識じゃない。寝ているときなどを考えればわかる。
意識は情報しか扱えない。言葉は情報の元だから、意識は言葉なら扱える。それだけのことである。私はスキーを習っているときに、スキーの本を数冊、読んだ。でもスキーは上手にならなかった。当たり前で、スキーは情報じゃないからである。
さて、酒場ライターとしての井上は、酒場ではいっつも酒を大量に飲む。意識が飛んでしまうことがあるのだ。
著書『たとえあなたが行かなくても店の明かりは灯ってる。』の内田樹せんせの解説(これだけでも買う価値ありの本だ)にある、
バッキーさんの書くものの過半は京都の町のさまざまな店で「気が遠くなるほどおそろしいくらい飲む」話である。
である。しかしババ酔いしてしもて完全に意識がなくなったら、これは書けない。仕事にならんのである。
だからそうならないためのひとつの方法として、コースターの裏にメモをして持って帰るのだ。
井上はそのスレスレ状態のとこ、紙一重をやってるから「日本初の酒場ライター」なんである。
その井上によって書かれたものは情報にほかならないだろうが、飲みまくって酔いまくって、書こうとして言葉がもつれたり、ほとんど言葉を言葉として運用できない、つまり何を書いてるか自分でもわからん(アホ状態に違いない)状態の時は、意識が変容するから情報も変容する。
だからこそ酒場ライターなのだし、そのスタンスからいけば、当然のこととして「取材などしないで書く」ということになる。
しっかし考えてみれば「取材(だけ)では書けない」というのは、これはキッツい背理である。
先の著書『たとえあなたが行かなくとも店の明かりは灯ってる。』の115ページにはこう書いてある。
飲みに行けば失うことばかりだ。お金も時間も愛も失うし頭も体も悪くなる。失言、失態、失禁、失敗だらけだ。けれどもそうすることによって大きなココロのケガから回避しているのかも知れない。
(略)
酒場への道 その5「負けてなあかん」
例えば、金があっても酒場では簡単に勝利投手になれない。街の手練れはお世辞という犠牲バントをしてみたり、急にフリーエージェント宣言を勝手にしてその時だけカネ持ちチームに入ったり、勝つ可能性が低くなっても高くなっても深酒泥酔没収試合という方向に持って行ったり、野球から将棋や野球拳に変わるように試合そのもののルールや形式を突然変えたりするからだ。
なかなかに魅惑的な「変容するスタンス」である。
そして今一度、養老先生にご登場願おう。
人間が「同じ」なわけはない。歳をとり、ついには死ぬ。どこが「同じ私」か。諸行無常と古人がいったとおりなのである。いつまで経っても同じなのは、情報なんですよ。でも人間は情報でない。それを取り違えたから、言葉が重いような、重くないような、変なことになったのである。変わらないのは私、情報は日替わりだ、などと思ってしまう。とんでもない、百年経っても、今日の新聞記事はそのままですよ。
毎日数時間インターネットに頭を突っ込んで、「新しいこと」を知ったと思っている。それはそれでいいけれど、インターネットの中にあるもの、つまり情報とは、つねに過去である。「済んでしまったこと」しか、あそこには入っていない。
情報化された酒はどこでも同じ味の酒である。
それがアイラ島のスコッチだとか、格付け銘醸ワインだとかというのは、何でも情報化して、それを「わたしという客が消費してやろう」という社会で通用するだけだ。
その情報はいったん記号化、データ化されると上書きされない限り変化しない。いつどこにいってもそのまま同じである。だから情報誌の酒やグルメの記事はひとつも面白くないのだ。
「わたしはわたし、同じ自己、同じ自我だ」というのもそれにほかならない。
繰り返すが人間は情報でない。
わたしが言ってるのではなく、養老孟司先生も内田樹せんせも、バッキー井上も言っている。
「頭の人ばかり ダメネ 人間は肉でしょ 気持いっぱいあるでしょ」(『全東洋街道』藤原新也)なのである。
ということで今回は、人さまの引用でほとんど書いてしまった。
もうおわかりだとは思うが、カメラは機械でありスペックだ。
それは変容しないから、そんなもの扱っても、いっこもおもろないから、酒場フォトグラファーを1日でやめてしまったのだ。
わたしとて残念だが、どうかわかってほしい。
堂島サンボア
大阪市北区堂島1-5-40
06-6341-5368