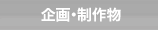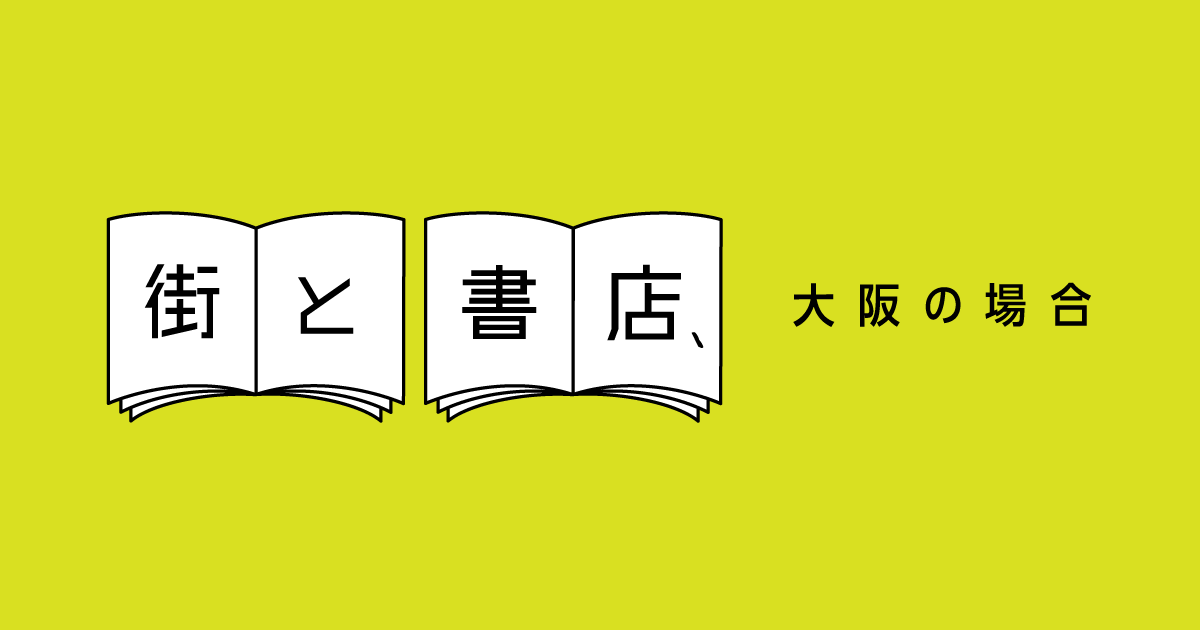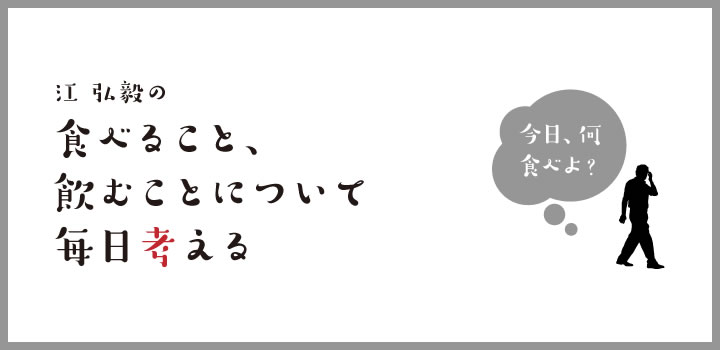担当/中島 淳
小林カツ代さんが製菓卸商「浅野商店」の末娘として生まれたのは昭和12年(1937)。
13〜14歳の時に徳島から大阪の船場に奉公に出され、23歳で大番頭に抜擢されるほどになった努力家の父・浅野徳太郎さんは、堀江の地にバターや小麦粉、ベーキングパウダー、食紅などの食用色素などを扱う製菓材料の卸問屋を興す。若くしてこのような商売で独立することが可能だった当時の堀江という街の特異性について、12月16日(土)のナカノシマ大学の講師であるノンフィクションライターの中原一歩さんは、著書でこのように書いている。
「大正から昭和にかけて、日本の近代食文化に大きく貢献した商人が堀江から誕生したことを、多くの日本人は知らない。牡蠣に含まれるグリコーゲンという栄養素に目をつけ、これをキャラメル菓子として商品化。『一粒三百メートル』というキャッチコピーと、おまけ商法で人気を博した、江崎グリコの創始者・江崎利一。そして、日本で初めてイースト菌の国産化に成功し、米国式連続自動釜を導入した、マルキ号製パンの水谷政次郎だ。」(『小林カツ代伝 私が死んでもレシピは残る』文春文庫)

大阪市立中央図書館は昭和36年(1961)に開館。平成8年(1996)に全面改築を果たして今日にいたる
生家である浅野家は大阪市西区御池通(みいけどおり)5丁目にあった。現在の西区北堀江3〜4丁目。戦後、南北を結ぶ幹線道路「新なにわ筋」が開通し、西側には大阪市立中央図書館が誕生する。
この巨大図書館にはご当地生まれのカツ代さんの著書も所蔵されているが、ふだん目にするのはほんの一部。しかし広大な書庫には約150点のタイトルが揃い(レシピ本だけでなく名作エッセイも)、もちろん閲覧も貸出も可能。蔵書はWEB検索できるのでぜひ窓口で尋ねてほしい。
大阪大空襲ですべてが灰になり、百舌鳥へ
両親の愛情をめいっぱい受けて育ったカツ代さんは昭和19年(1944) に大阪市立堀江国民学校(現・堀江小学校)に入学したが、内弁慶な彼女は学校に友達がいなかった。みんなが遊んでいるときに、ぽつんと一人遊びをしているような子供で、かつ不登校の常連だった。しかし、母の笑(えみ)さんは鷹揚に見守り、学校へ行くのを無理強いしなかったという。
カツ代さんが小学校に入った頃から、大阪の市街地はたびたび米軍の空襲に見舞われ、翌昭和20年(1945)3月13日深夜には、あの「大阪大空襲」が起きる。B29を100機以上連ねての絨緞爆撃だった。
「この空襲によって、木造家屋が集中していた堀江は壊滅した。大阪を代表する色町、堀江遊郭も、東洋一のマルキ号製パンの大工場も、江戸元禄の時代からこの地に根を張り生きてきた歴史ある商家も、そして徳太郎が一代で築きあげた浅野の家も、みんな灰になってしまったのである。」(同)
一家は、近所で食堂を営んでいた朝鮮人の友達のつてで、堺市百舌鳥の、戦国武将・筒井順慶(1549〜84)の子孫である「筒井家」の離れに疎開することになった。商家や問屋、工場などが密集する堀江から、町の大半が田んぼで、いたるところに自然が残る百舌鳥への環境の変化が、カツ代さんの人生を決定的に変えたといっても過言ではないと思う。

筒井家のシンボル、大クスノキ(堺市北区中百舌鳥町4-535)。内部は非公開
転校した堺市百舌鳥小学校では、当初「都会から来た垢抜けた女の子」に対する風当たりが強く、上級生からよく目をつけられていじめられたらしい。しかし、自然の生態系そのもののような筒井家の広大な敷地で思う存分に遊び回るだけでなく、戦中戦後の「ひもじさ」とはほとんど無縁の筒井家からもたらされる豊富な食材を使って母と姉が作る料理は、育ち盛りのカツ代さんにとって何よりの楽しみだった。学年が上がるごとに「成績優秀で、正義感の強い人気者」へと自己変革がはじまる。
「体がじょうぶになるにつれ、友だちもどんどん増えていきました。学校は、あいかわらず休みがちでしたが、友だちができはじめると、もともとは明るい性格なので、外交的になっていきました。五年生くらいになると、弱いものいじめしている男の子をポカリとやるくらい、ツヨークなっていました。」(小林カツ代『虹色のフライパン』国土社)
中原一歩さんも著書で筒井家の方に話を聞いている。
「『実は生前、カツ代さん本人がたずねてこられたことがありました。堺での暮らしは動物や自然が大好きだった自分にとって、町よりも楽しかったとおっしゃっていました。友だちや先生に恵まれて、同窓会のたびに、プライベートで足を運ばれているようでした』。カツ代は料理研究家としてデビューした後も、筒井家に対する恩義を忘れることはなかった。晩年まで、筒井家とは年賀状のやりとりがあったという。
(中略)結局、堺には三年ほど身を寄せていたが、その後、カツ代は再び大阪市内へと移り住む。しかし、よほどこの小学校の居心地が良かったのだろう。戦後、カツ代は大阪市内から、再建されたばかりの地下鉄と電車を乗り継いで、卒業まで、この小学校に通った。」(『小林カツ代伝』)
筒井家の敷地には、百舌鳥古墳群に属する「御廟表塚(ごびょうおもてづか)古墳」がある。カツ代さんの姉の節さんは、「裏山」と呼んでいたこの古墳にもカツ代さんとしょっちゅう登っていたと、弟子で料理研究家の本田明子さんが教えてくれた。
百舌鳥の中でも珍しい、街道沿いの登れる古墳
ここから先は筆者の話であるが、弊社刊のガイドブック『ザ・古墳群〜百舌鳥と古市 全89基』で89基の古墳を取材した際に、百舌鳥古墳群44基の中で最も印象に残ったのが、この御廟表塚古墳だった。

筒井家の、クスノキの近くにある「御廟表塚古墳」の石碑。この頃は墳丘に樹木があった(2017年12月1日・内池秀人撮影)
筆者は小学校6年の秋から高校卒業までの6年半、「百舌鳥夕雲町」「百舌鳥梅町」といずれも「百舌鳥」と名の付く町に住んでいた。前者は国内1位の「仁徳天皇陵古墳」、後者は同7位で美しい墳丘のシルエットに定評のある「ニサンザイ古墳」からいずれも徒歩3分の距離に自宅があった。古墳好きにとっては「世界遺産のスーパースター」のそばで、さぞかし羨ましい場所であることだろう。
しかし、10代のガキにそんなものの値打ちが分かるはずもない。
広大な古墳はたしかに自然の宝庫ではあったが、住民にとってほとんどの墳丘は「柵の向こう、濠の向こう」であり、その恩恵には与れない。周囲を歩くと四季の移ろいが感じられ、鳥や虫たちの声が聞こえて風情はあるのだが、それを「風情」と実感できるには若すぎた。
そんな少年時代は遥か昔になった2017年の12月に、古墳本の取材で初めて御廟表塚古墳を訪れた。
意外なことに、高校通学に利用した南海中百舌鳥駅からわずか徒歩5分の距離、自転車でたびたび前を通っていた「西高野街道」沿いにあったが、道からはよく見えなかった(というより、意識していなかった)。
百舌鳥で初めて「登れる古墳」を体験した日のことは忘れられない。44基ある百舌鳥古墳群の中で、墳丘に登れるのはわずか4基。その中でも墳丘長約85メートルの御廟表塚古墳はナンバーワンの大きさだ。
ライターの郡麻江さんもカメラマンの内池秀人さんも、それまで「見る」しかなかった古墳に「登れる」という要素が加わって興奮している。案内していただいた堺市博物館の学芸員・橘泉さんも、はしゃぐ取材班を見ながら楽しそうにしていた。

百舌鳥古墳群が世界遺産に登録され、案内板も設置された。山火事を避けるために、墳丘の樹木が伐採されたのは少し残念(2023年8月28日)
『ザ・古墳群〜百舌鳥と古市 全89基』が出版されて以降も、この御廟表塚古墳には用事のないときも何度も訪れては墳丘に登り、頂上から百舌鳥の集落や他の古墳を眺めて悦に入っていた。
こんな経験が子供時代に味わえていたら、百舌鳥に対する印象も少しは変わっていたかもしれない。あの時の興奮と墳丘のほっこり感を、小林カツ代さんは実は70年以上前に味わっていたのかと知ると、ちょっと他人とは思えなくなった。
小林カツ代さんと筒井家や百舌鳥とのつながりについては、中原さんの著書『小林カツ代伝 私が死んでもレシピは残る』をぜひ。
12月16日(土)のナカノシマ大学では、その中原一歩さんが東京から来阪して、とっておきのエピソードを話してくれます。