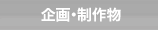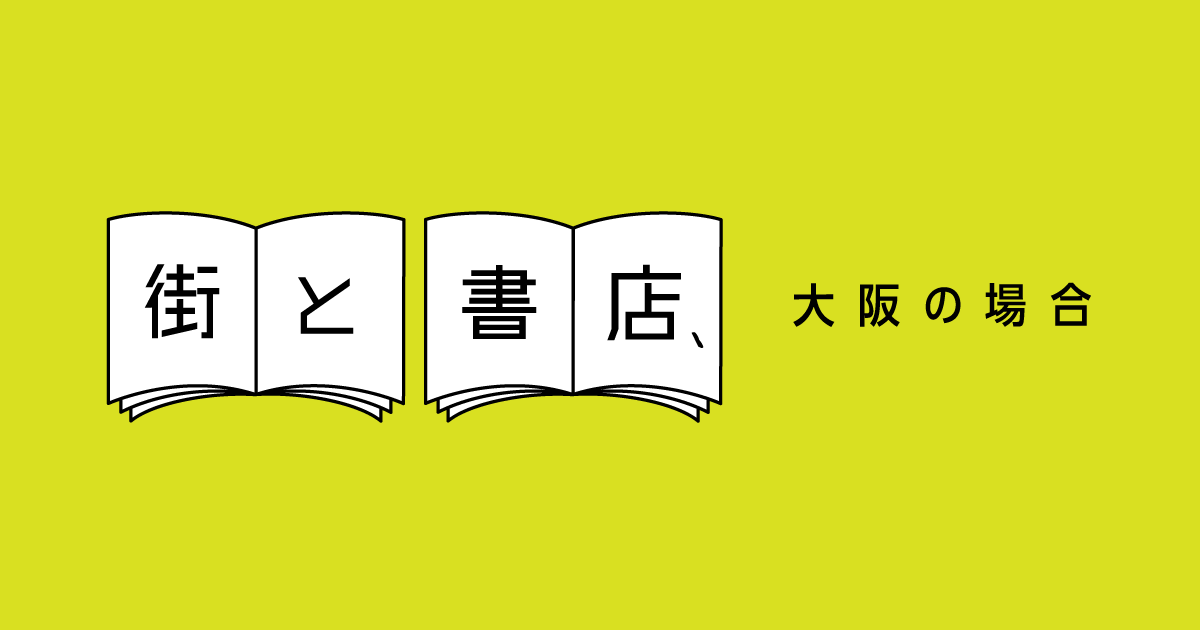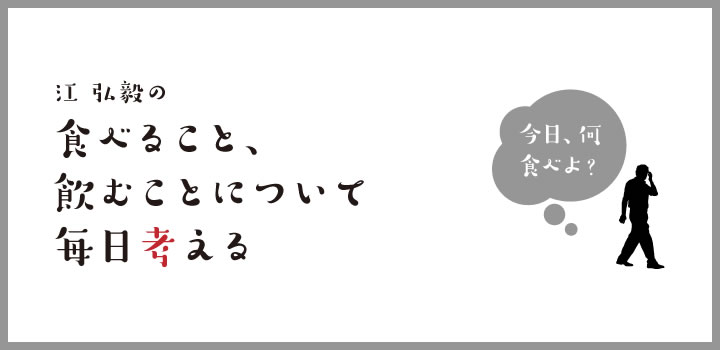ちょっと長くなりますが、筆者の昔ばなしを少し。
140Bを設立する前は、京阪神エルマガジン社に23年間(1983〜2006年)在籍していた。
LmagazineやSAVVY、Meets Regionalなどの編集に17年半、広告に1年半、そして最後の4年間は販売部に在籍していたが、自分の会社員生活では販売部での日々が最も充実していた時期だったように思う。
「出版社のカンバンを背負って、世の中に1冊でも多く届くように知恵を絞って、走り回った」という実感がすごくある。「ああしろ、こうしろ」とは言われずにのびのびと仕事させていただいたことは、ほんまに感謝している。
エルマガジン社は関西の雑誌業界ではそこそこ有名だと思っていたが、「日本の出版界」から見ると大海の小舟のような、ほんまにちっぽけな存在だと分かったのは販売部に移ってからだった。
そんな出版社が自社本を不特定多数の人に1冊でも多く届けるためには、本が売られている現場に行く必要がある。
「現場」はホームグラウンドの京阪神以外に、奈良も淡路も南紀もあったし、東京、名古屋、福岡……そして山陽・山陰路もあった。
*
JR西日本とのタッグで2004年にスタートした『西の旅』というシリーズMOOK(〜2008年)を売るにあたって、東京や、馴染みのなかった中国地方の書店や取次にお邪魔して、「平台のええとこになんとか置いたってください」と働きかける。こういう仕事は楽しかった。

初めて山陰エリアをメイン特集に打ち出した『西の旅』第4号(2004年11月10日発売)
その理由は、初めてお邪魔した島根・鳥取両県とも、書店の人たちが実にハートウォームな対応をしてくれたからである。
先方からすれば「大阪の雑誌社が私らの地元を紹介する? ふ〜ん……」というところだろうが、大昔からの親しい友人のような感じで接してくれて、少しでも実売が伸びるようにと注文書や表紙などに対して親身になってアドバイスしてくださった。今でも本当に感謝している。
販促ルートは、西は出雲市からスタートして、松江、米子、倉吉と東進し、最後は鳥取で終わって大阪に戻る、というもの。米子の、というより今井書店グループのシンボル的拠点[本の学校]の方にそのコースを説明すると、「じゃあ、帰りは必ず鳥取で定有堂書店」に寄らないとね」。
「テイユウドウ?」耳慣れない単語に面食らっていたら、その彼は「本好きの人が必ず寄る店ですよ」とうれしそうに言った。
「本好きが寄る店」という魔法のワードを聞いて、「それなら定有堂さんを鳥取の、いや今回の大トリにしよう」と、先に鳥取市内の他の書店をぐるぐる回った。
*
.jpg)
鳥取駅まで徒歩10分ほどの、若桜街道沿いにある定有堂書店(撮影/萱原健一)
夕暮れの鳥取駅前商店街に、この本屋さんはよく映えていた。
さして広くない店内の書棚からは「ええ匂い」が漂っていた。
店主は配達でまだ戻っていなかったが、「もうじき帰って来ますから、本でも見とってください」とおっしゃる奥さま(だったと思う)に従って、待たせていただく。
棚に付けられたタイトル(テーマ)を見ていたら退屈しない。
「小さな1冊の衝撃」という大タイトルの下に、棚の各区画にこんな小タイトルがぶら下がっていた。
「たった一人でも共同体」「ここから予見」「減速して自由に」
「名辞の虚妄」「ちいさな道しるべと自己肯定」「過剰適応をやめる」
「記憶は重荷ですから」……そういったコピーに、店の商品である本が並んでいる。

定有堂書店の棚。「穴が空くほど見た」人は多かったはずである(撮影/堀内菜摘)
ここに来た用事は、『西の旅』の注文書を渡して、できれば二桁仕入れてもらわんとアカンのだが、そのことをすっかり忘れてしまい、「さぁて、何買うて帰ろかな」にアタマが行ってしまう。
15分もした頃か、店主の奈良敏行さんが戻ってこられた。
腰の低い、穏やかでフレンドリーな人である。
奈良さんとはその後、こちらの書店に一度か二度ほど訪れて少しお話しした程度のことだったが、「何がどうというのはわからないけど、風通しがいい人だなぁ」という第一印象はずっと変わらなかった。
「本好きが集まる書店」というのは楽しそうだけど、「そうでない人間にとっては居心地が悪い」みたいなことがあったりする。けど、この店からはそんな匂いは全くしなかった。
子どもの頃からこんな本屋さんに通っていたら、さぞかしもっと人生楽しかったであろう。
鳥取駅に向かう帰り道の足取りは軽く、「スーパーはくと」の車中もゴキゲンだった。
……にもかかわらずズボラな筆者は、二度目か三度目の訪問のあと、会社を辞めて140Bという新しい仕事場を立ち上げたはいいが、鳥取で(というより定有堂書店で)売ってもらえそうな本を作っていないことを言い訳に、この店に立ち寄ることはなく、最後にお邪魔してから20年近くが過ぎてしまった、という次第である。
*
今年の3月9日(土)に摂南大学で、企業やら行政やら大学やらクリエイターやらいろんな現場に携わる人間が200人ほど集まる会合に出席した。この会合の名物は、あちこちの教室で同時に行われる「8分間のプレゼン大会」である。
同じ時間帯に、5つの教室でそれぞれ違う人間が違うテーマの発表をするプレゼンテーションが順繰りに行われる。
プログラムを見ても目移り必至だったけど、「なぜ人生には本が必要なのか? 三砂慶明」というタイトルを見て、「知らん人やけどここにしょうか」と教室に入った。
わずか3か月前なのに、彼が何を話していたかをほとんど覚えていないが(あかんやろ)、それまでざわざわしていた教室の空気が急に鎮まって、話者の言葉に場内が耳を澄ませていことだけは鮮明に覚えている。
プレゼンの最後に、この三砂氏が編集した『町の書店の物語 定有堂書店の43年』(作品社)という本が紹介された時に、懐かしさと、「あの、居心地のいい本屋がなくなってしまったのか……」という衝撃が一緒になってやって来た。

2024年3月発刊だが、すでに3刷。日本全国の「本好きが集まる書店」には必ずと言っていいほど置いてある
2日後にこの本を肥後橋の[Calo Bookshop and Cafe]で購入し、かつて「穴が空くほど見た」定有堂書店の棚のタイトルのように刺さりまくる、著者・奈良敏行さんの言葉(これを一つひとつ書いていたら夜が明ける)に何度もうなずいて、三砂慶明さんに「ナカノシマ大学で話してもらえませんか?」と頼んだ次第である。
*
2023年4月18日に43年の歴史を閉じた定有堂書店は、もう「記憶の中の書店」でしかないが、その「記憶を留めて呼び覚ます」人がいて、その人が編集した本が発刊された直後に偶然にも会うことができたのは、ラッキーだったという他にない。
そして、ここまで定有堂書店店主の奈良敏行さんの良さを引き出し、彼の哲学や思想を分かりやすい言葉で伝えた編集者(彼は、梅田鶴野町の関大ミライズにあるTSUTAYAの書店員でもある)には、「やりやがったな」というリスペクトである。
三砂氏は6月22日(金)のナカノシマ大学では、自らが編集した定有堂書店のことにはもちろん触れるが、大阪の本好きとしては、「定有堂のような書店が、大阪にはないんかいな?」ということを知りたいところである。
それで彼は今、大阪市内・府下にあるあちこちの書店を改めて訪れている。
どんな「大阪の本屋」の話が出るのか?
そして三砂氏が奈良敏行さんから直接聞いた、「人生に効くであろうお薦めの本」についても、当日のお楽しみにしてくだされ。
現在は75%まで埋まったいて、満席必至です。どうぞよろしく。

5月31日(金)、丸福珈琲店心斎橋PARCO店で行われた中川和彦氏(スタンダードブックストア店主・左)と三砂氏のトークイベント。定有堂書店をよく知る中川氏だけに、対話の呼吸とテンポがよく、みなさんどんどん引き込まれていきました