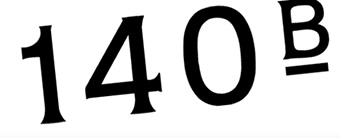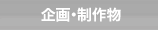担当/中島 淳
3月18日(火)のナカノシマ大学「メディアタウン扇町の意外すぎる歴史と、いま」に登壇する山納洋(やまのう・ひろし)さんは、まち歩きの主催や地域プロデューサーとして、あるいはミーティングの名ファシリテーターとして有名な人だが、大阪ガスネットワーク株式会社エネルギー・文化研究所の研究員というのが本職だ。
山納さんのプロフィールだけを見てもA4用紙がぎっしり埋まってしまうほどたくさんあるので、それはこちらを見ていただくことにして……→ https://www.og-cel.jp/area/h_yamanoh/index.html#l03
*
この日(2月22日)は、山納さんが2023年秋から拠点の一つにしている、劇場・映画館の複合施設「扇町ミュージアムキューブ」1階のカフェ[談話室マチソワ]にお邪魔した。マチソワの店主は3人いて、その一人が山納さんである。HPにはこうなっていた。


大テーブルでメモを取る人、小テーブルから参加する人……堅苦しくないのがええ感じ。山納さんは「店主」なのでカウンターでコーヒーを淹れつつ、トークに参加していた
この日のイベントは
■BIBLIOPHILE’S CAFE(本を紹介する会) 店主:やまのう
2/22(土) 16:00-18:00 参加無料(1ドリンク制)
お気に入りの本、面白かった本を持ってきて紹介し合う会です。
というもの。
この[談話室マチソワ]は、街場のカフェとはちょっと違っていて、趣旨をこのように紹介している。
※以下、談話室マチソワHPより
人々が集まり、お茶を飲みながら知らなかった人とも話ができるお店。自然なかたちでつながりやアイデアが生まれる。どこからも自由な、リラックスできる場所。マチソワはそんな空間です。
マチソワでは、スタッフがお客さんに話しかけ、お客さんの話に耳を傾けます。情報を発信するだけでなく、受け皿ともなり、有機的につなぎ合わせ、開放するメディアとして、劇場の片隅にひっそりと佇んでいます。
扇町ミュージアムキューブの廊下とマチソワの間には扉がない。「面白そうだな」と思ったらスッと入っていける。
知らない同士で話をするのが「ここでは普通」であるとみなさん認識しておられる。
みなさん、山納さん同様に聞き上手で、ひとりが本を紹介すると、次々と質問が出てきたり、自分の経験を語ったりして、それで話が盛り上がって……という好循環が続く。
読むべき本のネタは仕入れられるわ、自分の読んだ本についても興味を持ってもらえるわ、ですこぶる楽しかった。これも主催者の人徳であろう。山納さんは各人の「お気に入り本」の話が広がりすぎて制限時間をオーバーした時だけ、サッと切り上げて次の人に移る。そのあたりが実にウマい。
*
この日、参加者がとりあげた「お気に入りの本」は以下の通り。
●中村博史『大阪城全史』(ちくま新書)
●中島岳志・磯崎憲一郎・若松英輔・國分功一郞『「利他」とは何か』(集英社新書)
●石川智久『大阪 人づくりの逆襲』(青春新書)、『大阪が日本を救う』(日経BP)
●北川央『おおさか図像学』(東方出版)
●山田鐘人・作、アベツカサ・画『葬送のフリーレン』(小学館)
●『日本の家紋とデザイン』(パイインターナショナル)
●雑誌『デザインのひきだし』(グラフィック社)

山納さんの本の解説はフレンドリーかつ理路整然としていて、聞く側のストレスが全くない
●山崎亮『面識経済』(光文社)
⚫︎河井寛次郎『蝶が飛ぶ 葉っぱが飛ぶ』(講談社文芸文庫)
*
山納さんは3月18日(火)のナカノシマ大学に「扇町」というお題で講義するが、実はこの「扇町ミュージアムキューブ」は15年前まで大阪市水道局のビルで、水道局が移転した部屋に「MEBIC大阪(現在は本町の大阪産業創造館17階にある)」というクリエーターを育てるインキュベーションの拠点があって、山納さんはそこで働いていた。
その前は、神山の交差点近くにある小劇場演劇の拠点「扇町ミュージアムスクエア」にいたというから、まさに扇町の申し子のような人である。
だからナカノシマ大学は面白くなることは確実だと思うが、次回はもう少し扇町のことを書きます。