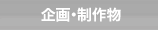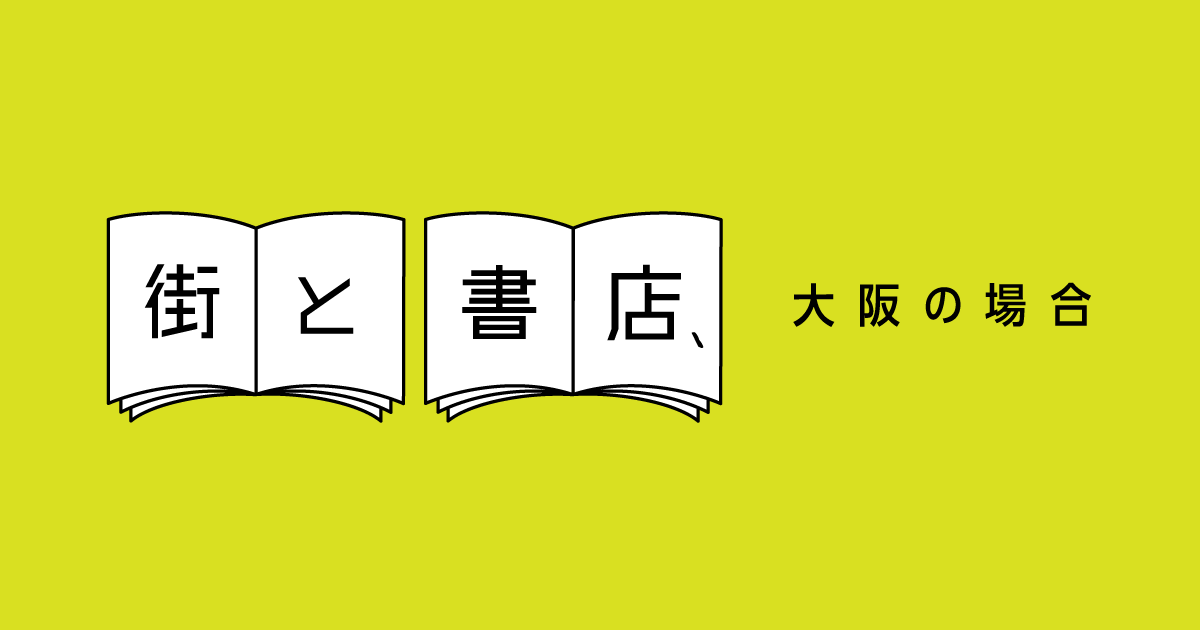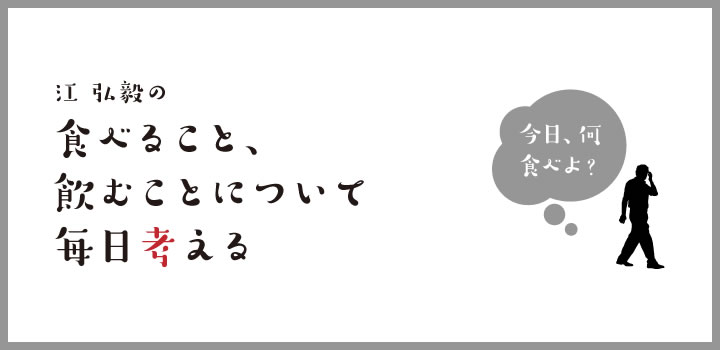担当/中島 淳
12月16日(土)は雨がいつ降るか分からないような天気だったが、平日夜のナカノシマ大学に漂う「仕事帰り」的な感じではなく、「休日に出てきました」的な、ちょっと華やいだ空気があった。
ワンショルダーの黒いエプロン、白ブラウス、ピンヒール、そして赤い口紅でさっそうとキッチンに立っていた料理研究家・小林カツ代さんに因んだものだからというのは、間違いなくあると思う。

よく通る声が中之島図書館3階の多目的スペースに響き渡っていた
通常は、「講義資料を投影し、受講者には簡単なレジュメを配布」というパターンだが、「投影」はカツ代さんにちなんだ動画を10分ほど流すだけで、あとは話だけでいきます、と中原さん。
最近は講義内容をパワポで投影、というパターンが多い。それはそれで講師の話す言葉が「プロジェクターの見出しや写真で強調される」ということで分かりやすい。しかし一長一短はある。
というのも、受講者は「画面」にばかり目が行って、肝心の「講師の姿」を見なくなってしまう。照明を落とすことが多いから余計である。当日の中原さんの選択は正しかったと思う。
*
話が始まったらすぐにみなさん引き込まれた。
1.中原一歩さんと小林カツ代さんの出会い
中原さんの『小林カツ代伝 私が死んでもレシピは残る(以下、カツ代伝)』(文春文庫)を読まれた方はご存じだと思うが、この評伝は著者(1977年生まれ)が二十歳の頃、カツ代さんに電話をするところから始まる。用件はとんでもない内容だった。
ピースボートの年越しクルーズ船に乗船してもらい、新年に黒豆を船上で振る舞ってほしい、ただしノーギャラ、ボランティアで……と。しかしカツ代さんは「面白いじゃない、私、行くわ」と即答し、そのあとストーリーが猛烈なスピードで動き出す。けれど読者の一人として私は、この「ホンマかいなの展開」を不思議に思っていた。
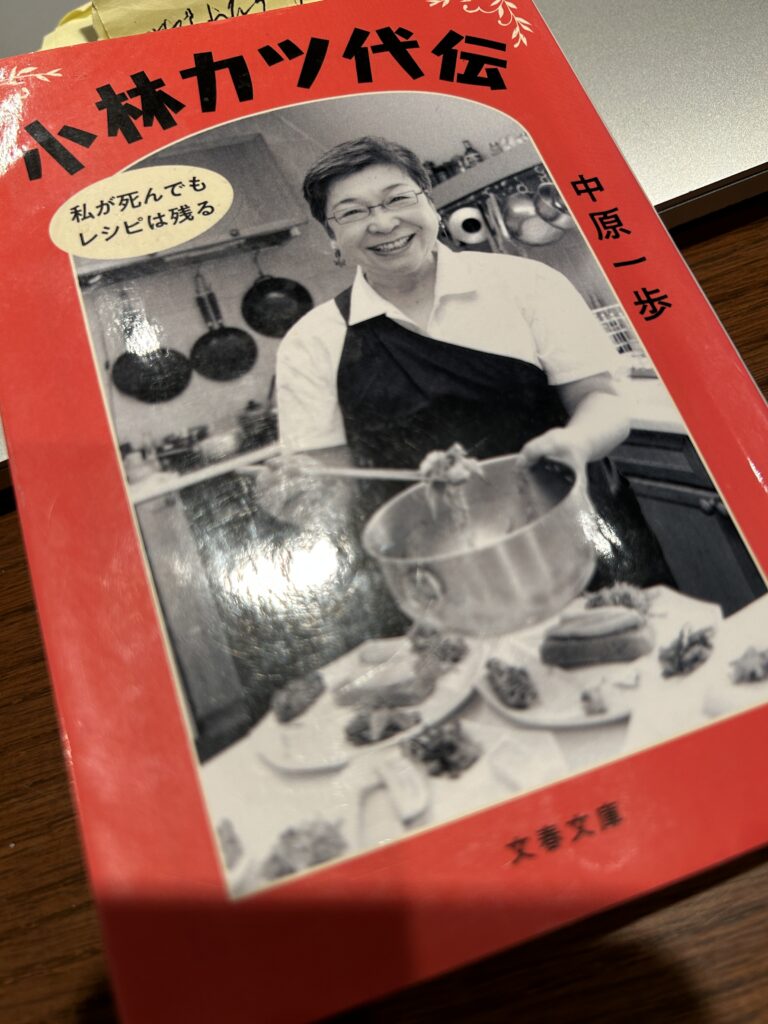
筆者の『小林カツ代伝』は肉じゃがを作るそばに置いたりして、もうボロボロである
(普通は、電話を取り次いだ人がこの無茶なリクエストの相手に、『先生は忙しい人なんですよ、無理です!』と言って話を終えるはずなのに、どうしてカツ代さんにつないだのだろうか……?)
その理由もこの講演で明らかになった。
1994年に「料理の鉄人」で陳建一を破って以降、講演や出張料理教室などの依頼が全国から殺到していた。カツ代さんが代表を務めるキッチンスタジオの人たちは依頼内容を彼女に伝え、「OK」が出たらあとは、弟子の本田明子さんをはじめスタッフが依頼者と詳細な打ち合わせをする、という流れで対応していた。
しかし、断らざるを得ない依頼もある。「せっかくのお話ですが……」というときはカツ代さんが直接、電話に出たり訪問客に伝えたりしていた。相手の気持ちをないがしろにしない、律儀な対応をする人だったのだ。
中原さんが電話をした時も、内容を聞いて取り次いだ人(コワい人だと恐れられていた加藤和子さん)はカツ代さんに電話を渡した。通常は「お断りモード」のはずだが、そうはならなかった。
「ケニアまで飛行機で行って、インド洋で乗船してもらうということだったんです。動物好きなカツ代さんは、サバンナにも行ける、といった期待もしていたのかもしれませんね。カツ代さんは稼いでおられたから、ノーギャラというのは彼女にとっては重要なことではなかったのでしょう。
わざわざアフリカまで行って、インド洋上で正月に千人分の黒豆を炊くなんて、世界で自分一人しかやらないだろう、ということにわくわくしたのだと思います」
カツ代さんは中原さんからの依頼に「ロマン」を感じてOKしたのであろうが、私はそれだけではないと思っている。以前も書いたように、彼の力強い声に、文字通り「ひとつ乗ってみるか」という賭けをしたのではないかと思う(このクルーズの顛末は本書をぜひ読んでください)。
2. 「自己革新」をし続けてきた人の家庭料理哲学

受講者に配布した資料
「カツ代さんはつねに、“I think”ではなく“I do”の人でした。クルーズの件も即決でしたが、長女のまりこさんが大学受験を控えていた時に、単身で2か月間アメリカに留学するんです、英語の読み書きができないのにもかかわらず(笑)。自分のあたらしい可能性を切り開くためには、躊躇する人ではありませんでした」
彼女の人生哲学は子供時代から一貫して
①興味を持つ ②知識を得る ③行動する ④世界が広がる
ということに貫かれていたという。
中学に入るとマンガを描きはじめ、手塚治虫に手紙を書いたのも(返事も来た!)、専業主婦時代に昼のワイドショーを観ていたらつまらないので「芸能人のゴシップを追うぐらいならお料理のコーナーをつくったらどうですか」と投書したのも(それがきっかけで自らが出演)、すべて同様の行動である。
カツ代さんは調理に際して「お醤油をチャーッとかけて」のような感覚的表現を多用したが、同時に、つねに「理屈」を大事にした。
「カツ代さんの頭の中には常に『?』と『!』の二つの符号がありました。
『?』は『なんでやろ?』『どうしたらいい?』、『!』は『あ、こうなんや』。発見と発明です。カツ代さんにとって、料理は科学、サイエンス(科学)とケミストリー(化学)なんです」
「家庭料理」とは、食べることで命をつなぐ大事なもの。カツ代さんにとっては夫と2人の子供がいる家庭で、時間とのせめぎ合いの中で毎日作り続けねばならないものであったが、いつでも満足できる料理が提供できるわけではない。この悩みが「時短料理」につながった。
「カツ代さんはある時、『料理は残酷や』とつぶやいたことがあります。その中で『おいしい、早い、安い』というところをずっと守り抜いた。家庭料理がレストランの料理と決定的に違うのは、『作る人が食べる人』ということです。天ぷらなら、揚げている人も食卓で熱々を食べるにはどうしたらいいか、と常に考え続けた。そして素材も調味料も、近所のスーパーで手に入るものしか使わなかった。『この料理は石垣島でも作れるかしら?』とよく言っていて、いつでも、どこでも作れるかどうかを常に気にかけていました」
その原則には厳しかったが、ストイックな人ではなく、いつもユーモアを忘れなかった。
「デパ地下で店員さんが『活きのいい車海老が入ってますよ!』と勧めても、カツ代さんは『ありがとう。でも私はいつお亡くなりになったか分からないようなブラックタイガーでいいの』と笑顔でスルーしていました。『塩少々』という表現も『◯グラム』ということではなく、『お焼香の時につまむでしょ? あんな感じ』とレシピ本にも書いていました」
3. 両親と大阪から「祝福」を受けた人が、言葉とレシピで祝福を贈った

投影しなくとも、話に引き込まれる。注意深くノートを取る人も
そして、自説に固執することはせず、「自分とは違う見方」を大事にした。
「カツ代さんには「絶対」というこだわりがなく、否定をしない人でした。結婚して東京に移り住んだ頃は甘い玉子焼きや濃いめの味付けが苦手だったそうですが、やがては慣れて、『これはこれで美味しいわよ』と東西両方のいいとこ取りをしていました。また、いつも鉄のフライパンを愛用していましたが、年を重ねると、もっと軽いテフロン加工のフライパンも使い、テフロンならではの料理を考案しました。
それは、否定されることなく育ったからだと思います。裕福な家庭でかわいがられ、ええもんを食べて育ったからこそ、あの味覚が育まれた。大阪・ミナミのカルチャーが小林カツ代を育てたんです。彼女の両親は味覚だけでなく、料理の腕が良かったことも見逃してはいけないと思います。カツ代さんの家庭料理はプロの技術に裏打ちされていました」
食事をすることに対しては、一食たりともおろそかにしない。内容も、その時間も、一緒に過ごす人も大事にした人だからこそ、「食べることを軽んじる人、権力を持ったエラそうな人」とは徹底的に闘った。大阪弁を話すこと、擬音で表現することも押し通したし、一緒に食事をする相手を大事にした。
「行政やテレビ局、出版社などのパーティーなどでカツ代さんがゲストに呼ばれるんですが、大概は、人のぬくもりが感じられないパーティー料理です。カツ代さんはそんな時、夜遅くであろうと僕に『食べ直ししよう』と電話をかけてきて、11時ごろに新大久保のお好み焼き屋に行ったことがありました。ドレス姿で煙モウモウの店に入って、服にも煙の匂いが付くのにお構いなしで、お好み焼きを2枚、汗だくでペロリと食べて『あ〜おいしかった!』なんてこともありました」
カツ代さんが鉄板の前で美味しそうにお好み焼きを食べる姿が彷彿としてくる。
*
最後に中原さんは、詩を描くことが大好きだったカツ代さんの自作の詩を朗読してくれた。
らくらくと らくらくと
料理づくりができたなら
人生どんなにらくでしょう
苦しいことや つらいこと
いっぱい いっぱいあるなかで
せめて日々のお料理は
底抜けに 明るく 楽しく作りたい
まゆにしわ寄せ作るより
ちょっとインチキしちゃったと
ウフッと笑って作りたい
それでも絶対大丈夫
お味見できる舌を持ち
おいしく おいしく作ろうと
思う心と手があれば
(中原一歩『小林カツ代伝 私が死んでもレシピは残る』〈文春文庫〉より)
*
講座の冒頭、カツ代さん動画の再生中に私のMacが調子が悪くなり、途中で二度ほど途切れてしまった。ほんまにお恥ずかしい限りである。改めて、中原さんをはじめお越しになったみなさまにおわびいたします。申し訳ありませんでした。
中原さんは、隣の席で動画を再生させようと冷や汗をかきながらもがいている私を横目に……
「こちらの中島さんはOsakaMetroのフリーマガジン(Metrono)にカツ代さんのことを書こうと、わざわざ東京まで取材しに来てくれたんです。それで文藝春秋で会うことになったのですが、結局、コメントがたった2行しか生かされていなかった(笑)。この出版不況のご時世に、たった2行のために東京に来られるとは、なんてコスパの悪い!(場内笑) でも逆にそれだけ信用できる人だ、と思いまして、今日はこちらに寄せていただきました」

11月10日発行『Metrono』第3号。駅員さんにお問い合わせを
自分が送った動画がちゃんと再生されなかったりすると、講師が機嫌を損ねて、それで場の空気が冷えたりすることがよくある。が、中原さんは私の失敗もネタに笑いをとって会場を温めていただいた。さすが40歳上のカツ代さんから「親友」とリスペクトされた人だけのことはある。手練れの対応にひたすら感謝しかない。ありがとうございました(ほんまは2行より、もうちょいありますw)。
*
会場には、カツ代さんの弟子で料理研究家の本田明子さんもわざわざ東京から受講しに来られていた。講師の中原一歩さんとはもう四半世紀のお付き合いである。本田さんもカツ代さんも登場するNHKの「きょうの料理〜65年続けたらギネス世界記録に認定されましたSP」は12月31日(日)の17:15に再放送される。お見逃しなく。
カツ代さんの姪の浅野貴子さんも、娘のわかなさんと一緒に受講しに来てくださった。貴子さんはカツ代さんの6歳上の姉・節さんの娘である。
「叔母は娘のまりこさんや息子の健太郎くんと同様に、自分の娘のように接してくれました。間違ったことをしていたら人前であろうとどこでも叱られました。今から思うと、それが本当に良かったのだと思います」
娘のわかなさんは料理人の道を志し、オランダでキャリアをスタートさせるという。
そして、西区北堀江にあったカツ代さんの生家が大阪大空襲で全焼し、一家が疎開した堺市百舌鳥からも、筒井家の谷妙さんと、中原さんを筒井家に紹介した辻要子さんがお越しになっていた。お2人は、中原さんが『カツ代伝』を執筆するにあたって7年前に取材した人である。
大阪市内から京都から神戸から北摂から河内から堺から、そして東京からも「カツ代さん好き」の方々が集結した2023年最後のナカノシマ大学は、これにて終了です。

カツ代さんが大好きだった千日前の[純喫茶アメリカン]でもチラシを置いていただいた。松竹のスターたちの公演チラシを差し置いて一等地に。随喜の涙
最後に、中原さんをご紹介いただいて取材にも立ち会ってくれたのみならず、ナカノシマ大学に合わせて『小林カツ代伝 私が死んでもレシピは残る』を会場で販売できるようにお骨折りいただいた文藝春秋の池延朋子さんをはじめ、チラシを置いていただいた飲食店、物販店、行政関係者のみなさまに心よりお礼申し上げます。
では、次回1月30日(火)にお会いしましょう。
どうぞ良いお年をお迎えください!