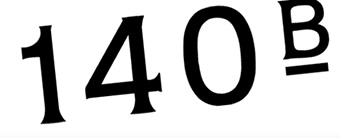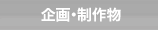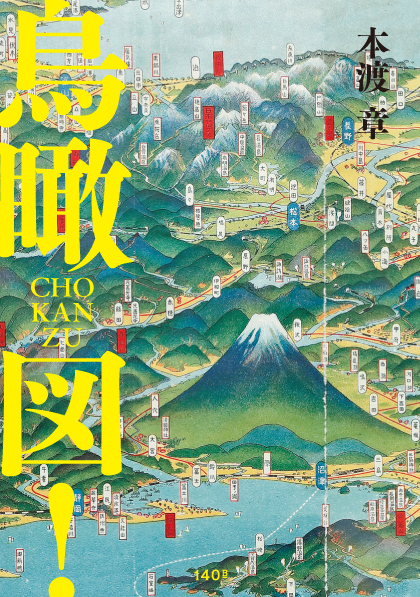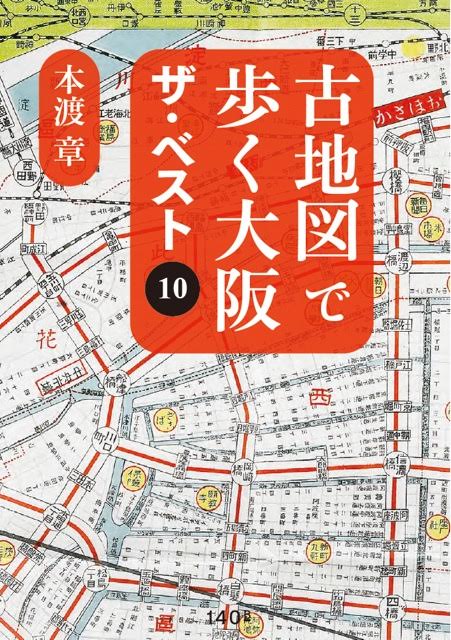2024年11月22日・本渡章より
【今回の見出し】
- 大阪ガスビル古地図サロン最終回と新サロンのお知らせ
- お知らせ・電子書籍のご案内・プロフィール
■大阪ガスビル古地図サロン最終回と新サロンのお知らせ
2024年11月22日をもって大阪ガスビル1階カフェ「feufeu」での古地図サロンは終了しました。
最終回は参加12人、公開古地図7点を囲んで、いつものように和やかなひとときを過ごしました。2018年1月26日開催の第1回から数えて全45回のご愛顧ありがとうございました。
※会場の1階カフェ「feufeu」はその後も大阪ガスビル改修工事が始まるまで営業していますので、皆様引き続きご利用ください。
「古地図サロン」初期の風景(2018年頃)



■ 2025年からは、次の2つのサロンでお会いいたしましょう。
★豆玩舎ZUNZO(宮本順三記念館)
2025年2月7日(金)午後2~4時、第8回古地図サロン「東風(こち)」
会場はグリコのおまけデザイナー、宮本順三さんの作品と世界の玩具のミュージアム。2023年9月から始まり、地図を通して大阪府域の歴史や暮らしを語る場に育ちつつあります。
近鉄八戸ノ里駅前。参加費(記念館入館料)700円(お茶付き)
2025年3月29日(土)午前10~12時、第1回サロンを開催。(第1回は春休み期間中につき、主に親子対象になる予定)
会場は江戸時代創業の老舗を改装した私設図書館。地域のコミュニティ的な場としても親しまれています。古地図サロンの詳細は未定ですが、所在地の西天満の地域活動を応援するかたちでスタートしたいと思います。
最寄りは大阪メトロ南森町・北浜・淀屋橋の各駅。
■ 2025年イベントのお知らせ
●「古代の鉄の文化と黒姫山古墳 」 主催・文学歴史ウォーク
1月12日(日)10~14時 南海高野線・北野田駅前集合
東文化会館での講演&黒姫山古墳・みはら歴史博物館の見学
2月3日(月) 10時~11時30分 河内国一之宮の枚岡神社と河内の歴史(教室)
3月3日(月) 10時~11時30分 参道とともに賑わう石切劔箭神社と河内の風土(教室)
3月17日(月) 10時~12時30分 石切劔箭神社~枚岡神社(現地)
●大阪古地図さんぽ
大阪24区を順番に歩いてめぐる「古地図さんぽ」講座を年数回開催しています。
2025年2月のテーマは都島区。開催日など詳細は大阪コミュニティ通信社まで。
●「明治~大正~昭和の大阪古地図展(仮題)」
大阪府立中之島図書館
開催決定! 期間は2025年4月のおよそ1カ月間、展示地図 100点余。
来春リニューアルされる展示室での最初のイベントになる予定です。
詳細はあらためてお知らせします。
● X(ツィッター)
X(ツィッター)始めました。本渡章 @hondo_akira1113
古地図以外の話題もいろいろ。その他まだ公開できませんが、進行中の案件あり。いずれご報告いたします。
一年間の連載(題字と似顔絵・奈路道程)に追加取材を加え、ブログの内容を大幅に刷新して書籍化が進行中です。刊行までブログ「大阪の地名に聞いてみた」をお楽しみください。
第12回 ここは水惑星サンズイ圏【前編・後編】
第11回 島の国の島々の街【前編・後編】
第10回 仏地名は難波(なにわ)から大坂、大阪へ【前編・後編】
第9回 人の世と神代(かみよ)をつなぐ神地名【前編・後編】
第8回 語る地名・働く地名【前編・後編】(仕事地名・北摂編)
第7回 古くて新しい仕事と地名の話【前編・後編】(仕事地名・河内編)
第6回 街・人・物・神シームレス【前編・後編】(仕事地名・泉州編)
第5回 場所が仕事をつくった【前編・後編】(仕事地名・大阪市中編)
第4回 花も緑もある大阪【前編・後編】
第3回 桜と梅の大阪スクランブル交差点【前編・後編】
第2回 続・干支地名エトセトラ&その他の動物地名【前編・後編】
第1回 大阪の干支地名エトセトラ【前編・後編】

●大阪古地図さんぽ
大阪24区を順番に歩いてめぐる「古地図さんぽ」講座を年数回開催しています。5月のテーマは淀川区。詳細は大阪コミュニティ通信社まで。
●動画シリーズ継続中!
本渡章の「古地図でたどる大阪の歴史」~「区」150年の歩み
大阪市のたどった道のりを、それぞれの土地の成り立ちと経済、文化など多様な要素を持つ24の「区」から見つめなおすシリーズ。続編はしばらくお待ちを。詳細は大阪コミュニティ通信社まで。
第2回番外編 府と区と市の関係について再考
第2回その2 西へ西へと流れた街のエネルギーと水都の原風景…西区
第2回その1 「江戸時代の大坂」と「明治以後の大阪」の架け橋となった巨大区…西区
第1回その3 平成の減区・合区が時代のターニングポイント
第1回その2 大正~昭和は人口爆発、増区・分区の4段跳び時代
第1回その1 大坂三郷プラスワン、4つの区の誕生
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
【古地図ギャラリー休眠のお知らせ】
2020年9月から2023年11月まで、東畑建築事務所・清林文庫の所蔵地図、鳥瞰図絵師の故・井沢元晴氏の作品を中心に紹介してきた古地図ギャラリーは休眠期間に入りました。過去20回の公開作品には現役の鳥瞰図絵師、青山大介氏の作品や本渡章所蔵の古地図も含まれています。ラインアップは下記の通りです。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
★過去20回の古地図ギャラリーで公開した全40作品
第20回(2023年11月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「大阪新町夕陽廊の賑」安政5年(1859)
第19回(2023年9月)
①東畑建築事務所・清林文庫より黄華山・画「花洛一覧図」文化5年頃(1808)
第18回(2023年7月)
①東畑建築事務所・清林文庫より池田奉膳蔵「内裏図」
第17回(2023年5月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「地球萬國山海輿地全図」
②青山大介作品展2023
第16回(2023年3月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「天王寺・石山古城図」
第15回(2023年1月)
①東畑建築事務所・清林文庫より長谷川圖書「摂津大坂図鑑綱目大成」
第14回(2022年11月)
①東畑建築事務所・清林文庫より久野恒倫「嘉永改正堺大絵図」
②鳥観図絵師・井沢元晴の作品より「私たちの和田山町」
第13回(2022年9月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「淀川勝竜寺城跡全図」
第12回(2022年7月)
①東畑建築事務所「清林文庫」より秋山永年「富士見十三州輿地全図」
第11回(2022年5月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「大日本分境図成」
第10回(2022年3月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「新改正摂津国名所旧跡細見大絵図」
③鳥観図絵師・井沢元晴の作品より「笠岡市全景立体図」
第9回(2022年1月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「暁鐘成・浪花名所独案内」
②本渡章所蔵地図より「大阪市観光課・大阪市案内図
③鳥観図絵師・井沢元晴の作品より「躍進井原市」
第8回(2021年11月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「友鳴松旭・大日本早見道中記」
②本渡章所蔵地図より「遠近道印作/菱川師宣画・東海道分間絵図」「清水吉康・東海道パノラマ地図」
③鳥観図絵師・井沢元晴の作品より「吉備路」
第7回(2021年9月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「石川流宣・江戸図鑑綱目坤」「遠近道印・江戸大絵図」
②本渡章所蔵地図より「改正摂津大坂図」
③鳥観図絵師・井沢元晴の作品より「倉吉市と周辺 文化遺跡絵図」
第6回(2021年7月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「石川流宣・日本海山潮陸図」「石川流宣・日本国全図」
②本渡章所蔵地図より「大阪師管内里程図」
③鳥観図絵師・井沢元晴の作品より「倉敷美観地区絵図」
第5回(2021年5月)
①2007清林文庫展解説冊子・2019清林文庫展チラシ
②本渡章所蔵地図より「近畿の聖地名勝古蹟と大阪毎日」
③フリーペーパー「井沢元晴漂泊の絵図師」・鳥観図「古京飛鳥」「近つ飛鳥河内路と史跡」
第4回(2021年3月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「大阪湾築港計画実測図」
②本渡章所蔵地図より「大阪港之図」
③鳥観図絵師・井沢元晴の作品より「福山展望図」
④鳥観図絵師・青山大介の作品より「梅田鳥観図2013」
第3回(2021年1月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「江戸切絵図(尾張屋版)」「摂津国坐官幣大社住吉神社之図」
②本渡章所蔵地図より「摂州箕面山瀧安寺全図」
③昭和の伊能忠敬・井沢元晴の鳥観図より「小豆島観光絵図」
第2回(2020年11月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「メルカトル世界地図帳」「オルテリウス世界地図帳」
②本渡章所蔵地図より「A NEW ATLAS帝国新地図」「NEW SCHOOL ATLAS普通教育世界地図」
③昭和の伊能忠敬・井沢元晴の鳥観図より「大阪府全図(三部作)」
第1回(2020年9月)
①東畑建築事務所・清林文庫より「ブレッテ 1734年のパリ鳥観図」
②昭和の伊能忠敬・井沢元晴の鳥観図より「ふたつの飛鳥と京阪奈」
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
東畑建築事務所「清林文庫」は、同事務所の創設者東畑謙三が蒐集した世界の芸術・文化に関する稀覯本、約15000冊を所蔵。建築・美術工芸・絵画・彫刻・考古学・地誌など分野は幅広く、世界有数の稀覯本コレクションとして知られる。古地図に関しても国内外の書籍、原図など多数を収め、価値はきわめて高い。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
鳥観図絵師・井沢元晴(1915~1990)は戦後から昭和末までの約40年間に、日本各地を訪ねて多くの鳥観図を描き、昭和の伊能忠敬とメディアで紹介された。活動の前半期にあたる戦後の20年間は「郷土絵図」と呼ばれた鳥観図を作成。その多くは、子供たちに郷土の美しさを知ってもらいたいとの願いをこめて各地の学校に納められ、校舎に飾られた。学校のエリアは主に西日本。「郷土絵図」の活動は60年代半ばまで継続し、新聞各紙にとりあげられた。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
鳥観図絵師・青山大介(1976~)神戸生まれ。高校時代に都市鳥瞰図絵師の第一人者、故・石原正氏の鳥観図に出会い、感銘を受け、独学で鳥瞰図絵師を志す。2011年、制作に3年半をかけた「みなと神戸バーズアイマップ2008」を完成。2013年発行の「港町神戸鳥瞰図2008」は神戸市の津波避難情報板に採用された。以後、多数の作品を発表し、都市鳥瞰図の魅力を発信。2022年の「古の港都 兵庫津鳥瞰図1868」は同年開館の兵庫津ミュージアムのエントランス展示作品となる。2023年、神戸市文化奨励賞受賞。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●電子書籍のお知らせ
本渡章の著書(古地図・地誌テーマ)のうち、電子書籍になった10冊(2022年末現在)は次の通りです。
(記載の刊行年は紙の書籍のデータです)
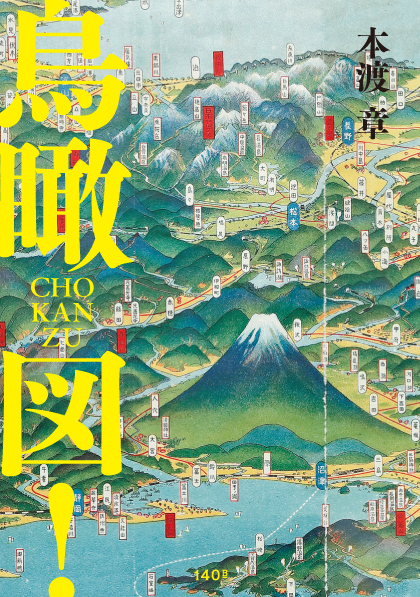
【『鳥瞰図!』140B・刊(2018年)
思考・感情・直観・感覚…全感性を目覚めさせる鳥瞰図の世界にご案内。大正の広重と呼ばれた吉田初三郎の作品群を中心に、大空から見下ろすパノラマ風景の醍醐味を味わえます。併せて江戸時代以来の日本の鳥観図のルーツも紐解く、オールカラー・図版多数掲載の決定版。
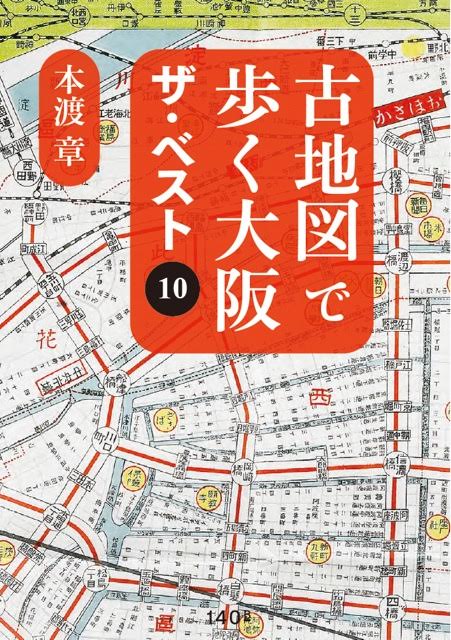
『古地図で歩く大阪 ザ・べスト10』140B・刊(2017年)
梅田・中之島・御堂筋・ミナミ・天満・京橋・天王寺。阿倍野・住吉・十三・大正・平野の10エリアを古地図で街歩きガイド。さらに博物館、図書館、大書店、古書店での古地図探しの楽しみ方、大阪街歩き古地図ベストセレクション等々、盛りだくさんすぎる一冊。オールカラー・図版多数掲載。
*上記2冊は各電子書籍ストアでお求めください
*下記8冊は創元社(オンライン)の電子書籍コーナーでお求めいただけます
『図典「摂津名所図会」を読む』創元社・刊(2020年)
大阪の地誌を代表する「摂津名所図会」の全図版を掲載。主要図版(原寸大)には細部の絵解きの説明文、その他の図版にもミニ解説を添えた。調べものに便利な3種類の索引、主要名所の現在地一覧付。江戸時代の大阪を知るためのビジュアルガイド。
『図典「大和名所図会」を読む』創元社・刊(2020年)
姉妹本『図典「摂津名所図会」を読む』の大和(奈良)版です。主要図版(原寸大)には細部の絵解きの説明文、その他の図版にもミニ解説を添え、3種類の索引、主要名所の現在地一覧も付けるなど「摂津編」と同じ編集で構成。江戸時代の奈良を知るためのビジュアルガイド。
『古地図が語る大災害』創元社・刊(2014年)
記憶の継承は防災の第一歩。京阪神を襲った数々の歴史的大災害を古地図から再現し、その脅威と向き合うサバイバル読本としてご活用ください。歴史に残る数々の南海トラフ大地震の他、直下型大地震、大火災、大水害の記録も併せて収録。
『カラー版大阪古地図むかし案内』(付録・元禄9年大坂大絵図)創元社・刊(2018年)
著者の古地図本の原点といえる旧版『大阪古地図むかし案内』に大幅加筆し、図版をオールカラーとした改訂版。江戸時代の大坂をエリアごとに紹介し、主要な江戸時代地図についての解説も収めた。
『大阪暮らしむかし案内』創元社・刊(2012年)
井原西鶴の浮世草子に添えられた挿絵を題材に、江戸時代の大坂の暮らしぶりを紹介。絵解きしながら、当時の庶民の日常と心情に触れられる一冊。
『大阪名所むかし案内』創元社・刊(2006年)
江戸時代の観光ガイドとして人気を博した名所図会。そこに描かれた名所絵を読み解くシリーズの最初の著書として書かれた一冊。『図典「摂津名所図会」を読む』のダイジェスト版としてお読みいただけます。全36景の図版掲載。
『奈良名所むかし案内』創元社・刊(2007年)
名所絵を読み解くシリーズの第2弾。テーマは「大和名所図会」。全30景の図版掲載。
『京都名所むかし案内』創元社・刊(2008年)
名所絵を読み解くシリーズの第3弾。テーマは「都名所図会」。全36景の図版掲載。
※その他の電子化されていないリアル書籍(古地図・地誌テーマ)一覧
『古地図でたどる 大阪24区の履歴書』140B・刊(2021年)
『大阪古地図パラダイス』(付録・吉田初三郎「大阪府鳥瞰図」)140B・刊(2013年)
『続・大阪古地図むかし案内』(付録・グレート大阪市全図2点)創元社・刊(2011年)
『続々・大阪古地図むかし案内』(付録・戦災地図・大阪商工地図)創元社・刊(2013年)
『アベノから大阪が見える』燃焼社・刊(2014)
『大阪人のプライド』東方出版・刊(2005)

.jpg)