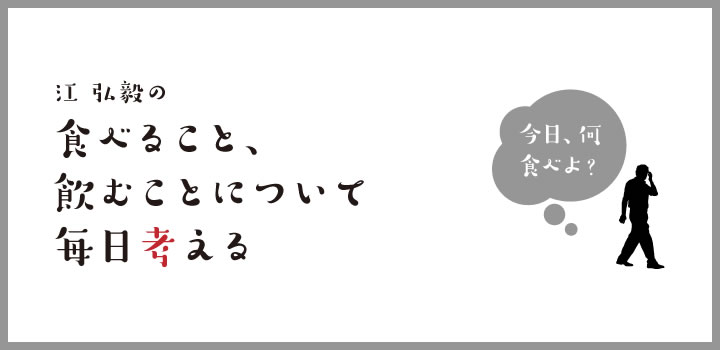10月5日
大阪 福島 鮨ふみ
9月3日に開店したばかりの『鮨ふみ』、だんじり祭の週と連休に行かなかっただけで、毎週行っている。
理由はうまいからだ。このうまいというのは、鮨屋に限っていえばグルメ的にどうだというのではなくて、自分に合うかどうかなのだ。だから他の類の店と鮨屋はジャンルが違う。うどん(のだし)もお好み焼きもそんな感じで、「合う/合わん」というのがベースだと思うが、鮨だけが高いわな、なんて思うが、10月に入っては2日、5日と連発してこの店に行っている。
鮨屋に限っていえば、開店したばかりの店に通うというのは今まで経験したことがない。だから今回のこの店のオープンは、いろんな発見があって楽しくて仕方がない。
この日、エビは開いて横にして四角く成形してにぎって出してくれたり、コチの昆布締めも初めてで楽しい限りだ。
しかしいつも注文するのは決まっていて、トロか中トロ。中トロは鉄火巻きにしてもらう。理由なんかない。自分がこの店ではそうした方がおいしいと思うからだ。鰻も絶対言うな。2カン食べることもある。煮ハマグリはツメ(タレ)がおいしくて、一遍にファンになった。そして干瓢巻き。
そんなところで鮨は極端な話、「この店、合う」と思えば、毎日同じ店で同じ席に座って同じネタを食べるのがおいしい。そうわたしは思っている。
鮨屋はほかの食べもん屋と比べて、高くてなかなか叶うことではないが、自分のフトコロに合わせて、回数よりも行く店そのものは「我慢」しているつもりだ。そしてそんな店でもトロやアワビ連発はしない。これも「我慢」だ。
ある種のグルメたちは、そこのところが分からない。一軒の店に行ったら次の店に行き、その味を比べる、みたいなことがおいしいのだと思っている。こと鮨屋に関しては、違うなと思う。
江戸前鮨の店や職人について「ええ鮨にぎるな」と実感するのは、3カンぐらい食べてちょっと酒が回ってくると、腹が減ってきて、「しまあじ」「蛸」「エビ」というぐらいに10カンぐらい連発して、普段食べないあまり好物でないネタまでもいってしまうことだ。
大間産のマグロや明石の鯛いや加太やで、とかやどこそこの米とか酢とか、そんなのは関係ない。記号ではなくじぶんの感覚だ。
わたしは毎日同じ鮨屋で同じ席に座って同じネタを食ベ、毎日同じように酒を飲む客(だいたい大工とか左官とかプリキ屋とかの職人系だった)が多い町で生まれ育ったのだが、残念なことに万博あたりを期に職人の姿が見えなくなった。近所に3軒あった鮨屋は閉店してほかの飲食店になっている。気がつけばもうない。
つまり職人の客がいなくなり、鮨をにぎる職人もすぐ後を追うようにしていなくなったのだ。70年代が所謂高度経済成長の中期かいつかにあたるのかは知らないが、わたしが記憶する鮨屋ついては、今そういう光景がなくなったことだ。
- 大阪 北新地 山守屋
- 大阪 京橋 上海ママ料理
- JR芦屋 月桂冠
- 大阪 京橋 岡室酒店直売所
- 神戸 中山手 一平
- 大阪 ハービスプラザ バーヒラマツ
- 大阪 北新地 バー・アルディ
- 尼崎 阪神尼崎 大貫
- 大阪 堂島 アマルール
- 大阪 千日前 重亭
- 東大阪 布施風月
- 大阪 船場 美々卯本店
- 金沢 犀川大橋 8番ラーメン
- 大阪 ハービス大阪 ちゃんと。
- 尼崎 阪神尼崎 やすもり
- 大阪 梅田地下街 江戸寿司
- 神戸 福原 丸萬
- 神戸 三宮 バー・ローハイド
- 大阪 道頓堀 バー・ウイスキー
- 神戸 元町 バー・ムーンライト
- 大阪 西梅田 ロウリーズ・ザ・プライムリブ大阪
- 大阪 ミナミ 金太郎
- 大阪 西梅田 オイスタールーム
- 大阪 心斎橋 まつりや
- 大阪 生野 西光園
- 神戸 元町 グリルミヤコ
- 大阪 黒門市場 浜藤
- 神戸 元町 グリルミヤコ
- 大阪 西梅田 TGIFRIDAYS
- 神戸 東門街 酒肆 大関
- 大阪 北新地 堂島サンボア 黒門さかえ(27日、29日)
- 大阪 北新地 アリラン亭
- 大阪 文の里 松寿し
- 神戸 福原 丸萬
- 神戸 県庁前 帝武陣
- 大阪 福島 鮨ふみ
- 大阪 福島 ミチノ・ル・トゥールビヨン
- 大阪 福島 ミチノ・ル・トゥールビヨン
- 大阪 福島 鮨ふみ
- 大阪 駅前第4ビル 七福神
- 大阪 北新地 山守屋
- 神戸 元町 林記厨房
- 自宅 チキンラーメン
- 神戸 元町 サイゼリア
- 大阪 堂島 ニュー神戸
- 神戸 北野 ル・パッサージュ
- 鶴橋 空
- 新世界 だるま
- 神戸 北野 ビストロ近藤亭
- 東大阪 近大前 盛華園/てらまえ/鳥寿
- 自宅 おかず
- 大阪 駅前第1ビル キングオブキングス
- 大阪 ハービスPLAZAENT バルバッコア
- 大阪 新梅田食道街 樽金盃
- 神戸 元町 蛸の壺
- 神戸 元町 四興樓
- 大阪 福島 えべっさん
- 大阪 北新地 バー・エルミタージュ
- 大阪 船場 𠮷野寿司 平岡珈琲店
- 大阪 桜橋 深川
- 神戸 三宮 のんちゃん
- 大阪 北新地 甚五郎
- 大阪 北新地 ういすたりあ
- 大阪 天満 肴や
- 大阪 天五 上川南店
- 大阪ミナミ 八幡筋 キャベツプラザ育
- 大阪 福島 ミチノ・ル・トゥールビヨン
- 大阪 駅前2ビル 山長梅田店
- 神戸 三宮 六角亭
- 大阪 北新地 旬彩堂
- 大阪 堂島 パウゼ(18日、20日)
- 大阪 北新地 ちんみん亭
- 大阪 北新地 黒門さかえ(12日、19日、20日、23日)
- 自宅 大丸の地下で買ってきたもの
- 大阪 鰻谷 バー・ヘミングウエイ
- 自宅 てっちり
- 神戸 三宮 源平
- 神戸 元町 太田屋
- 神戸 三宮 美作
- キューバ ハバナ(5日〜17日)
- 神戸 丸萬
- 神戸 パブケネス
- 大阪 はり重カレーショップ
- 神戸 古屋
- 大阪 福喜鮨
- 大阪 北新地
- 神戸 さんちか
- 自宅
- 江弘毅
編集者・著述家。雑誌ミーツリージョナルを立ち上げ、1993〜2005年編集長を務める。
2006年編集出版集団140B創立。著書「有次と包丁」(新潮社〕、「飲み食い世界一の大阪」(ミシマ社)など多数。毎日新聞連載中の「濃い味、うす味、街のあじ。」の単行本化、140Bから7月15日発売。