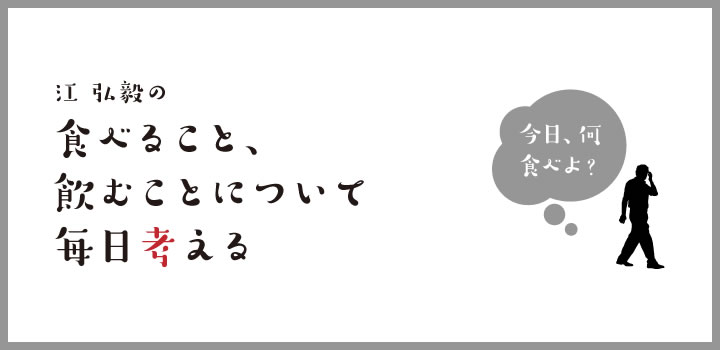1月14日
大阪 ハービス大阪 ちゃんと。
90年代前半から2000年頃にかけて、無国籍創作料理店の『ちゃんと。』 が一世を風扉した。すぐに心斎橋に森田恭通デザインによる基幹店『ケンズダイニング』をオープンさせ、東京やニューヨークにも進出したことを憶えている。
創作料理というのは素性が分からない思いつき料理のような感じで、個人的には口が合わないというか、なんとなく好きになれなかったが、この「キムチの王様」はその頃何回か食べた。
第1回日経レストランのメニューグランプリを獲得したとかで、絶対これを注文しなくては、といった大変な人気を博した。この時代はまだまだ情報誌やグルメ誌が世の中に対して絶大な影響力を持っていた。
この「キムチの王様」について、1店1ヶ月あたり1tのキムチを使う、という爆発的な人気ぶりをメディアは報じたのだが、わたしは、阪神淡路大震災の後、2000年になってぐらいから自分のやっている雑誌や書いている文章で、なんとなく『ちゃんと。』的な飲食店に一線を画すようになった。浪花座の跡にたこ焼きや串かつを売りにしたフードテーマパークの「道頓堀極楽商店街」の空気も街的ではないと感じたし、広告代理店的でありファッション誌的な「仕掛け」の匂いがしていたのが鬱陶しかった。
ちょうど編集しているミーツ別冊の「三都市本」シリーズが東京でプレイクし始めた最中で、「こうさんは避けているな」などと、そのころ 『ちゃんと。』や極楽商店街をプロデュースしていたソルトコンソーシアムの井上盛夫くんに面と向かって言われたりした こともある。
事実、10万部は軽かった02年の「大阪本」のタイトルは「うわベだけのお店紹介は、もういいんです。」で、トップページは『松葉家本舗』のおじやうどんと『道頓堀今井』のきつねうどん、続いて『八重勝』『グリルマルヨシ』『オモニ』と続いていた。
誤解のないように言っておくが「キムチの王様」はうまい。鯛、貝柱、海老の海鮮、貝割れ、三つ葉の野菜やナッツ類を白菜キムチで包んだこの料理は傑作だと思う。
皿の上のことを言ってるのではない。時代というものに揮発させている空気のことを言ってるのだ。
久しぶりに「キムチの王様」を食べてそんなことを思う。
- 大阪 北新地 山守屋
- 大阪 京橋 上海ママ料理
- JR芦屋 月桂冠
- 大阪 京橋 岡室酒店直売所
- 神戸 中山手 一平
- 大阪 ハービスプラザ バーヒラマツ
- 大阪 北新地 バー・アルディ
- 尼崎 阪神尼崎 大貫
- 大阪 堂島 アマルール
- 大阪 千日前 重亭
- 東大阪 布施風月
- 大阪 船場 美々卯本店
- 金沢 犀川大橋 8番ラーメン
- 大阪 ハービス大阪 ちゃんと。
- 尼崎 阪神尼崎 やすもり
- 大阪 梅田地下街 江戸寿司
- 神戸 福原 丸萬
- 神戸 三宮 バー・ローハイド
- 大阪 道頓堀 バー・ウイスキー
- 神戸 元町 バー・ムーンライト
- 大阪 西梅田 ロウリーズ・ザ・プライムリブ大阪
- 大阪 ミナミ 金太郎
- 大阪 西梅田 オイスタールーム
- 大阪 心斎橋 まつりや
- 大阪 生野 西光園
- 神戸 元町 グリルミヤコ
- 大阪 黒門市場 浜藤
- 神戸 元町 グリルミヤコ
- 大阪 西梅田 TGIFRIDAYS
- 神戸 東門街 酒肆 大関
- 大阪 北新地 堂島サンボア 黒門さかえ(27日、29日)
- 大阪 北新地 アリラン亭
- 大阪 文の里 松寿し
- 神戸 福原 丸萬
- 神戸 県庁前 帝武陣
- 大阪 福島 鮨ふみ
- 大阪 福島 ミチノ・ル・トゥールビヨン
- 大阪 福島 ミチノ・ル・トゥールビヨン
- 大阪 福島 鮨ふみ
- 大阪 駅前第4ビル 七福神
- 大阪 北新地 山守屋
- 神戸 元町 林記厨房
- 自宅 チキンラーメン
- 神戸 元町 サイゼリア
- 大阪 堂島 ニュー神戸
- 神戸 北野 ル・パッサージュ
- 鶴橋 空
- 新世界 だるま
- 神戸 北野 ビストロ近藤亭
- 東大阪 近大前 盛華園/てらまえ/鳥寿
- 自宅 おかず
- 大阪 駅前第1ビル キングオブキングス
- 大阪 ハービスPLAZAENT バルバッコア
- 大阪 新梅田食道街 樽金盃
- 神戸 元町 蛸の壺
- 神戸 元町 四興樓
- 大阪 福島 えべっさん
- 大阪 北新地 バー・エルミタージュ
- 大阪 船場 𠮷野寿司 平岡珈琲店
- 大阪 桜橋 深川
- 神戸 三宮 のんちゃん
- 大阪 北新地 甚五郎
- 大阪 北新地 ういすたりあ
- 大阪 天満 肴や
- 大阪 天五 上川南店
- 大阪ミナミ 八幡筋 キャベツプラザ育
- 大阪 福島 ミチノ・ル・トゥールビヨン
- 大阪 駅前2ビル 山長梅田店
- 神戸 三宮 六角亭
- 大阪 北新地 旬彩堂
- 大阪 堂島 パウゼ(18日、20日)
- 大阪 北新地 ちんみん亭
- 大阪 北新地 黒門さかえ(12日、19日、20日、23日)
- 自宅 大丸の地下で買ってきたもの
- 大阪 鰻谷 バー・ヘミングウエイ
- 自宅 てっちり
- 神戸 三宮 源平
- 神戸 元町 太田屋
- 神戸 三宮 美作
- キューバ ハバナ(5日〜17日)
- 神戸 丸萬
- 神戸 パブケネス
- 大阪 はり重カレーショップ
- 神戸 古屋
- 大阪 福喜鮨
- 大阪 北新地
- 神戸 さんちか
- 自宅
- 江弘毅
編集者・著述家。雑誌ミーツリージョナルを立ち上げ、1993〜2005年編集長を務める。
2006年編集出版集団140B創立。著書「有次と包丁」(新潮社〕、「飲み食い世界一の大阪」(ミシマ社)など多数。毎日新聞連載中の「濃い味、うす味、街のあじ。」の単行本化、140Bから7月15日発売。