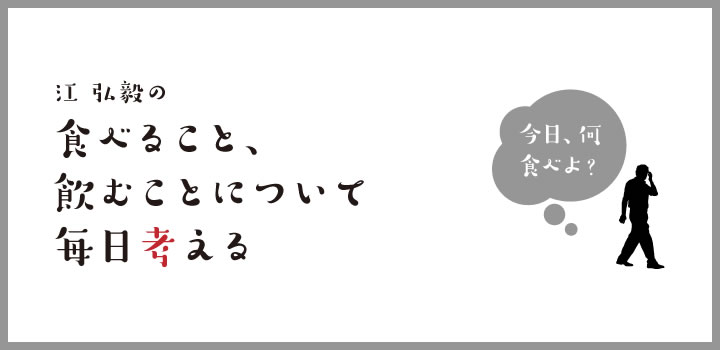5月15日
大阪 北新地 甚五郎
取材がてら[甚五郎]へ。一人ではよう行かんので、北新地の大先輩についてきてもらう。
昭和四年創業、名物胡瓜巻きの店。表の石碑に「元祖 起う里満き 鮓甚五郎」とある。「きうりまき」の登録商標を持っていたそうだ。それに遠慮して「カッパ巻き」という言い方が広まったのもあながち嘘だとは言えない。
その「きうりまき」であるが、ものの本には「紀う里満き」と書かれていたがどう見ても「記う里満き」である。念のため阪大招聘教授の髙島幸次せんせに写真をメールで送って判読していただく。すると、
どっちも間違いです(笑)
「起う里満き」です。
紀・記・起の崩し字を添付しましたので、ご自分で納得ください。
とのこと。この先生の博学はもちろん、こういう時のセリフがおもろい。大阪の学者である。
この店の胡瓜巻きを含め、大阪の鮨については朝日新聞の記者だった篠崎昌美さんが戦前の大阪を書いている『続・浪華夜ばなし』(朝日新聞社)に、興味深い記述がある。著者・篠崎さんは明治25年(1892)大阪市西区生まれ。
「東京式の握りずしが大阪に現われたのは、大正前期に鉄砲屋がやり始め、関東震災後になって南地に福喜、道頓堀に幸ずしが現われ、これが評判になって南地に立食い専門のすし捨やすし常が繁盛した。料亭化したものに島之内の松ずし、曾根崎の胡瓜巻専門の甚五郎などがあった」
アジのキズシ、炊き合わせ、鉄火巻き、胡瓜巻きと進む。ビールに酒、酒、酒。
いやはやこうして見ると、鉄火や胡瓜巻きの皿が、東京や京都ではなくとても大阪な感じがしてものすごくいい。今日は8つに切られて出てきたが、普通は6つ切りで出てくる。
- 大阪 北新地 山守屋
- 大阪 京橋 上海ママ料理
- JR芦屋 月桂冠
- 大阪 京橋 岡室酒店直売所
- 神戸 中山手 一平
- 大阪 ハービスプラザ バーヒラマツ
- 大阪 北新地 バー・アルディ
- 尼崎 阪神尼崎 大貫
- 大阪 堂島 アマルール
- 大阪 千日前 重亭
- 東大阪 布施風月
- 大阪 船場 美々卯本店
- 金沢 犀川大橋 8番ラーメン
- 大阪 ハービス大阪 ちゃんと。
- 尼崎 阪神尼崎 やすもり
- 大阪 梅田地下街 江戸寿司
- 神戸 福原 丸萬
- 神戸 三宮 バー・ローハイド
- 大阪 道頓堀 バー・ウイスキー
- 神戸 元町 バー・ムーンライト
- 大阪 西梅田 ロウリーズ・ザ・プライムリブ大阪
- 大阪 ミナミ 金太郎
- 大阪 西梅田 オイスタールーム
- 大阪 心斎橋 まつりや
- 大阪 生野 西光園
- 神戸 元町 グリルミヤコ
- 大阪 黒門市場 浜藤
- 神戸 元町 グリルミヤコ
- 大阪 西梅田 TGIFRIDAYS
- 神戸 東門街 酒肆 大関
- 大阪 北新地 堂島サンボア 黒門さかえ(27日、29日)
- 大阪 北新地 アリラン亭
- 大阪 文の里 松寿し
- 神戸 福原 丸萬
- 神戸 県庁前 帝武陣
- 大阪 福島 鮨ふみ
- 大阪 福島 ミチノ・ル・トゥールビヨン
- 大阪 福島 ミチノ・ル・トゥールビヨン
- 大阪 福島 鮨ふみ
- 大阪 駅前第4ビル 七福神
- 大阪 北新地 山守屋
- 神戸 元町 林記厨房
- 自宅 チキンラーメン
- 神戸 元町 サイゼリア
- 大阪 堂島 ニュー神戸
- 神戸 北野 ル・パッサージュ
- 鶴橋 空
- 新世界 だるま
- 神戸 北野 ビストロ近藤亭
- 東大阪 近大前 盛華園/てらまえ/鳥寿
- 自宅 おかず
- 大阪 駅前第1ビル キングオブキングス
- 大阪 ハービスPLAZAENT バルバッコア
- 大阪 新梅田食道街 樽金盃
- 神戸 元町 蛸の壺
- 神戸 元町 四興樓
- 大阪 福島 えべっさん
- 大阪 北新地 バー・エルミタージュ
- 大阪 船場 𠮷野寿司 平岡珈琲店
- 大阪 桜橋 深川
- 神戸 三宮 のんちゃん
- 大阪 北新地 甚五郎
- 大阪 北新地 ういすたりあ
- 大阪 天満 肴や
- 大阪 天五 上川南店
- 大阪ミナミ 八幡筋 キャベツプラザ育
- 大阪 福島 ミチノ・ル・トゥールビヨン
- 大阪 駅前2ビル 山長梅田店
- 神戸 三宮 六角亭
- 大阪 北新地 旬彩堂
- 大阪 堂島 パウゼ(18日、20日)
- 大阪 北新地 ちんみん亭
- 大阪 北新地 黒門さかえ(12日、19日、20日、23日)
- 自宅 大丸の地下で買ってきたもの
- 大阪 鰻谷 バー・ヘミングウエイ
- 自宅 てっちり
- 神戸 三宮 源平
- 神戸 元町 太田屋
- 神戸 三宮 美作
- キューバ ハバナ(5日〜17日)
- 神戸 丸萬
- 神戸 パブケネス
- 大阪 はり重カレーショップ
- 神戸 古屋
- 大阪 福喜鮨
- 大阪 北新地
- 神戸 さんちか
- 自宅
- 江弘毅
編集者・著述家。雑誌ミーツリージョナルを立ち上げ、1993〜2005年編集長を務める。
2006年編集出版集団140B創立。著書「有次と包丁」(新潮社〕、「飲み食い世界一の大阪」(ミシマ社)など多数。毎日新聞連載中の「濃い味、うす味、街のあじ。」の単行本化、140Bから7月15日発売。